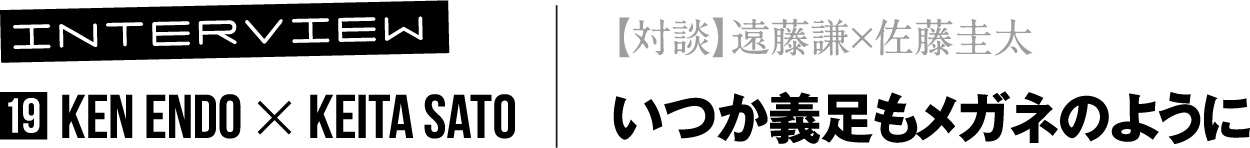
義足がメガネのような存在に
YMFS「ギソクの図書館」にしても、その後に展開される「BLADE FOR ALL」にしても、素晴らしいなと思うのは、機会を提供する場所の創造、ですよね。運動する機会と巡り合う、スポーツを始めるきっかけとなる出会い、やはりそこがパラスポーツの一番難しいところなのかなと。
佐藤僕は足を切断した時、浜松医科大学医学部附属病院に入院していたんですけど、そこのリハビリの先生と松本市の義足メーカーの方が、日常用義足ではなく、スポーツ用義足を使って走れることが僕の今後の人生にプラスになるんじゃないか、と考えてスポーツ用義足を用意してくれたんです。それが走り始めるきっかけとなったんです。そこでまず、自分の肉体が動き始めて。そしてもうひとつ、僕の心が動き始めたのは、パラ陸上のトップアスリートの方々とお会いする機会があったおかげです。彼らの走る姿を見たり、実際にお話しを聞かせてもらって、障害に対する心の部分のコンプレックスを払拭することができたんです。
YMFSなるほど。運動をする機会に出会うと同時に、実際にスポーツを通じて障害を克服した人たちとの出会いもすごく大事だということですね。
佐藤やはりロールモデルじゃないですけど、そういう人材の存在も大事だと思うので、もうちょっと仲間を増やしていかないとダメだなと感じますね。
遠藤あと、これは残された課題の一つだと思っているんですが、走る場所、機会があることは知っていても、そこへ行く勇気がないという人も潜在的には結構多いんじゃないじゃないですかね。とにかくまずは、地方自治体、あるいは医療従事者が、初期の段階で、こういうのもあるよっていうオプションとして、スポーツ用の義足を提示してあげられるようになるといいですよね。足を切るっていうネガティブな現実に幾つかのポジティブな選択肢を用意してあげられるようになればいいのかなと。
佐藤遠藤さんはよく、義足がメガネのように捉えられるようになるといい、って言うんです。だってメガネをかけなければいけなくなっても、人はそんなに大騒ぎしないですよね。つまり義足っていうのは別に特別なモノじゃなくて、誰もがそれを使うことになる可能性はあるし、たとえそうなっても特に大事ではないんだ、と。
僕は足を切ったとき、すごく嫌な思いもしたし、当然ネガティブな感情も持ちました。でも義足がメガネのような存在になってしまえば、まあ仕方ないか、ちゃんと生活はできるしな、ってなれると思うんです。僕自身が嫌な思いをしたからこそ、そういった思いをしない人が一人でも増えてほしいなあと思いますね。
遠藤走るっていうのは、本来、一番敷居が低いスポーツですよね。でももし、それすらできない状況が起こっているとしたら、その阻害要因はもちろんいろいろあるとは思いますが、やっぱりお金の問題は避けて通れないと思うんです。その解決にはやはり新しいエコシステムを作らなければならないし、僕自身そこにチャレンジしたいと考えています。
<次のページへ>










