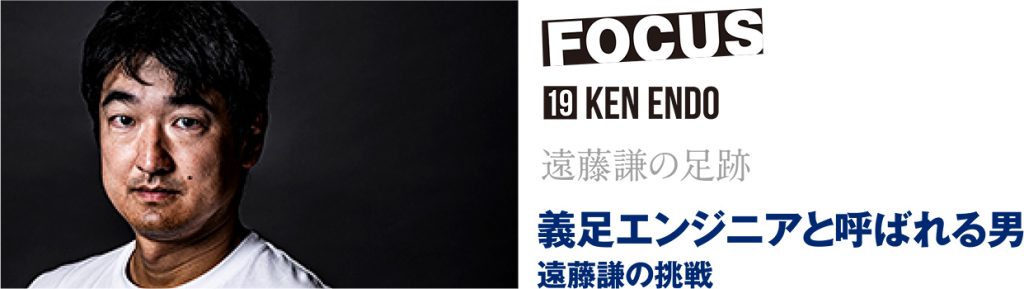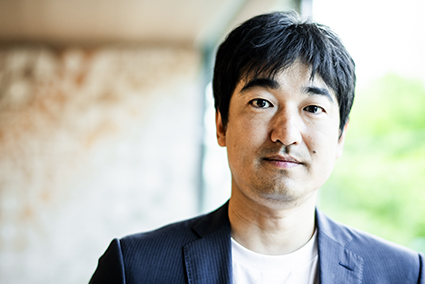『無い』ということ、そこには『大きな可能性がある』
ラボには世界中から、実に様々な才能を持った様々な立ち位置の人々がいた。元宇宙飛行士、世界中で使われているコンピュータの暗号技術を作った研究者、ロボット掃除機の会社の創立者、アフリカの小国シエラレオーネからの留学生。入学して3年目には、インド人のラボメイトに誘われてジャイプールを訪れ、本当にお金がない人たちに現地のプラスチック、まるでゴミのような材料を使って製作した義足を無償で提供する人々の活動に触れる、そんな体験もした。ハイテクノロジーだけがソリューションではなく、違う文化の中で、使えるものを使って問題を解決してゆく、そんな取り組みもまた必要であることを理解した。
メディアラボを仕切っていたのは、ヒュー・ハーという教授だった。若い頃は将来有望なロッククライマーだったハーは、17歳の時、ある登山の最中に遭難する。3日後、救助はされたものの両足は凍傷のために膝から下を切断、そこから義足ユーザーになった。しかし彼はその後もロッククライミングを続け、岩登りに適した義足を独自に開発し、かつては登れなかった断崖まで制覇してしまう。
ある日ハー教授は研究室で義足について議論している時、遠藤の足を指さして、こんなセリフを口にする。
「なあケン、君の足はこれから歳をとってどんどん衰えてゆく。でもオレの足はどんどんアップグレードしてゆくんだよ!」
There is no such a thing as disable person. There is only physically disabled technology. HUGH HERR
――世の中に身体障害者はいない。技術のほうに障害があるだけだ。By ヒュー ハー
これが7年と言う長い時間を過ごしたメディアラボで、遠藤が学んだ様々なことの根底にある哲学だった。
遠藤自身の言葉に変換すると、その哲学はこんなふうに訳すこともできる。
「『無い』ということは、つまりそこには『大きな可能性がある』ということなんです」
そしてその可能性を生み出すのがエンジニアの役割なのだと遠藤は信じている。
帰国、そして義足のエンジニアへ
2012年6月、遠藤はマサチューセッツ工科大学からPh.D.の学位を授与され、ボストンでの生活にピリオドを打ち、帰国後はソニーコンピューターサイエンス研究所の研究員に就任した。
ロボット義足の開発は面白いから継続したい、インドにも行きたい、そして競技用義足の開発も未来があるからやってみたい。やりたいことはいくつもあった。
きっかけは南アフリカ出身の義足のブレードランナー、オスカー・ピストリウス選手だった。ピストリウスは、2012年7月、ロンドンの地で、両足義足の陸上競技選手として初めてオリンピックへの出場を果たした。遠藤が健常者の大会に初めて参加することになったピストリウスの姿を初めて見たのは2007年だった。遠藤は即座に確信した。いずれ義足のランナーがウサイン・ボルトの持つ100m世界記録を更新する、と。まるで新しい人間を見ている気分だった。
自ら開発した義足ブレードで世界最速のランナーを誕生させたい、その瞬間に立ち会いたい。ボストンで義足の研究に携わりながら、遠藤にはもう一つの目標(あるいは強烈な好奇心)が生まれていた。
<次のページへ>