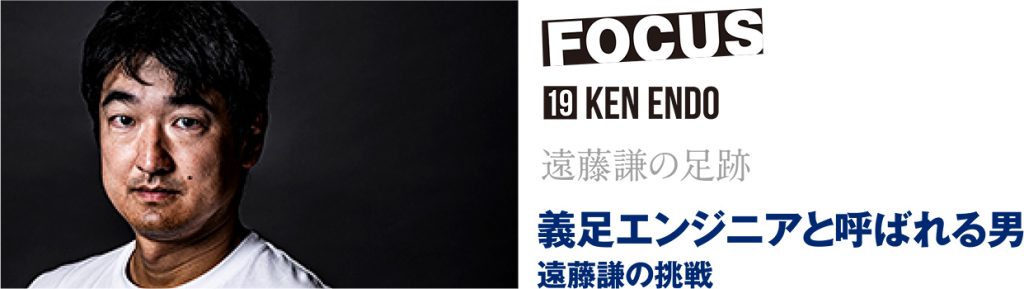MITメディアラボという名の研究室
大学に入学して以来、ひたすらロボットと対峙してきた23歳の若者は、人生で初めて、ロボットの向こう側にいる人間という存在を意識し、どんな命も、この世界の理不尽さ、あるいは死というものから逃れることはできないことを理解した。
あれがターニングポイントでしたね、と遠藤は言う。
2004年9月、仙台で開催された国際学会で、遠藤はアメリカのボストン、マサチューセッツ工科大学(MIT)の大学院に、メディアラボという名の研究室があり、そこでは最先端のロボット義足が研究されていることを知る。
自分の持つロボット研究を活かすことで、もしかしたら足を失った友に最高の新しい足を作ってあげられるかもしれない。遠藤は、発表を終えたアメリカ人研究者の一人に話しかけてみた。自分は今修士課程なので、それを終えたらあなたのラボに行ってみたい、と。
彼は遠藤の年齢をたずねてこう答えた。
「24歳か。だったらすぐにアプライしなよ。アプライの期日は12月、三ヶ月あればなんとかなるさ」
翌2005年の春、遠藤はボストンに到着する。
ボストン、MITメディアラボで過ごした日々
異国での研究者生活、ボストンでの最初の日々は大変だった。
英語は人並み以上に勉強してきたつもりだったが、いざ現地で生活を始めてみると、様々な国からやってきた人々が話すさまざまな癖のある英語に苦戦することになった。
そして本業の方は、さらに大変だった。当たり前だ。遠藤はそれまで機械工学を学んできたが、あたらしい領域はコンピューターサイエンス、分野はまったく異なった。それはつまり、ほぼ全てが一から始まることを意味する。しかも2年後にはクオリファイング・イグザムと呼ばれる、研究を行うために必要な知識や能力を修得しているか審査する試験に合格しなければならない。その試験をパスできなければ、それ以上、メディアラボでの研究は続けられなくなる。
本人は意識していなかったが、日々彼にのしかかるストレスは相当なものだったようだ。突発性難聴。ある日、遠藤の耳は聞こえなくなってしまった。耳の中に水が入ったような感覚が1週間ほど続き、クリニックでは「風邪かも」と診断されたが、その後、メンタルヘルスのセクションへと連れてゆかれ、パキシルという薬を渡された。調べてみると、それはセロトニンの働きを強めるいわゆるうつ病のための薬だった。
決して順調な毎日とは言えなかったが、メディアラボでの学びの時間、ロボット義足の研究はまさに彼が期待していた通りのものだった。
モノを作り、それがちゃんと動き、そして問題解決につながるという一連のプロセスがエンジニアとしての面白みだ、と遠藤は言う。
彼がそれまで研究してきた二足歩行ロボットは、歩くことそのものが目的だった。しかし人間を対象としたロボット義足は、それを身につけた人が歩けるようになった、だけでは終わらない。日常的に使えるようになるか、さらには楽しく歩けるようになるか。このモノ作りの先には、ロボット義足を身につけたそれぞれの人の心が続いていた。
日本での研究は、まず師事する先生がいて、学生や研究者はその下で勉強させてもらう、そんなスタイルだった。自分の作ったモノが社会で活きていようがいまいが、遠藤に当事者としての意識はなかった。しかしボストンは違った。自分の作ったモノは論文を書くためではなく、社会にポジティブな変化をもたらすために存在しなければならなかった。
<次のページへ>