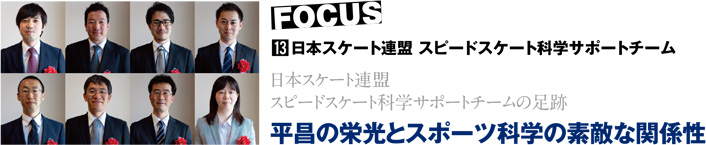スポーツチャレンジ賞
理屈としては正しいかもしれない

しかし、ことはそう簡単ではないのだと横澤は付け加える。先頭交代の回数を減らしたほうがいいのは数値的に誰でもわかる。入れ替わる方法も、確かに大きく膨らんだほうが理屈としては正しいのかもしれない。しかしその正しく見えることをコーチが現場で試す、しかも真剣勝負の場でそれを試すとなると、リスクを伴うそれなりに決断力のいる作業となるからだ。
「受け入れられるまでに時間がかかるのはしょうがないし、提案する側にも、決断する側にも、根気のいる作業であると思います。あとは、必ずしも科学者の主張がいつも正しいとは限らない、ということも忘れてはいけないですね。たとえ理屈上は正しくても、やるべきじゃないことはあるんです。理屈上正しいことをそのタイミングで選手に実行させることが果たして正しい選択なのかどうか、そこは科学者にはわからない。競技の現場の人のみが判断できることですから」
少しずつ、少しずつ、ヨハン・デビットは科学サポートチームのデータと分析をチームに取り入れてゆき、女子チームパシュート日本チームは平昌の地で金メダルを獲得する。しかも五輪新記録のおまけをつけて。
先頭交代をできるだけしない、それを主張し続ける紅楳には、ヨハンから“ミスター・ノーチェンジ"のニックネームが与えられたほどだったが、結果的にその“ミスター・ノーチェンジ"の元で黙々と各々の役割を果たし続けた科学サポートチームの方向性は正しかったし、その方向性を採択したヘッドコーチも正しかったことになる。
しかし当の紅楳はいたって冷静な反応を見せ続ける。平昌大会での金メダルはさすがに嬉しかったけれど、勝つべくして勝ったという安堵感の方が強かった。そしてその感覚は他のメンバーも変わらないはずだ、と彼は考える。
「なぜなら、自分たちをさらに上回るパフォーマンスを相手が出せば、1位の座は奪われます。けれど、だからと言ってこれまでにやってきた研究や分析が間違っていたわけではないんです。だから、科学サポートチームの面々は基本的にみんな、目の前の勝敗には一喜一憂しない、はずですよ」
交流会の最後、司会の女性に促され8人の科学サポートチームメンバーは壇上で関係者の前に整列し、一人一人が今回の受賞に対するコメントを求められる。彼らは照れ臭そうにマイクを受け取り、短く、しかし心のこもった謝辞を述べると、次のメンバーにマイクを渡してゆく。

そんな彼らを見て、日本スケート連盟スピードスケート強化部副部長を務める黒岩彰はひと言添える。
「科学というのは本来、表に出てきてはいけないもの、まさに縁の下で煤まみれになって、這いずり回るような存在なんです。科学は現場よりも絶対に先に出てはいけない、科学が競技の現場をリードすることがあってはいけないんです。でもね、科学なくしては、世界には勝てないんですよ!」
<了>
「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる