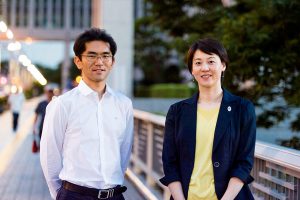スポーツチャレンジ賞

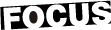
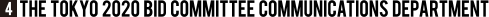

オリンピック・パラリンピックはいかにして決まるのか

写真提供:東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
オリンピック・パラリンピックの招致活動は、現在の規定では、大会開催の9年前にまず申請ファイルを提出することから始める。そのファイルはIOCによって精査され、正式に立候補都市を承認。そしてその1年後、IOCは調査団をそれぞれの国に送り、その結果も詳細なリポートとして公にされるのだ。
立候補した国は様々な招致活動を行えるが、基本的に海外におけるアピ—ルは最終投票の約8ヶ月前までは禁止され、それぞれの委員を自国に招待することもできない。
そして大会開催の7年前、投票権を持つ百数名のIOCの委員たちが投票により開催都市を決定する。委員たちの顔ぶれは各競技団体のトップ、各国のオリンピック委員会の会長、ロイヤルファミリー、アスリート、スポーツ振興に造詣の深い人々が様々な属性で存在する。
IOCとしてはどの国を通過してゆくことがオリンピック・パラリンピックそのものの発展に寄与するかを考えるが、それぞれの委員にはそれぞれのバックボーンがある。競技団体によって開催都市の嗜好は当然変わってくるし、世論によってもIOCの委員たちの方向性が変わってくる。
2009年10月、2016年のオリンピック・パラリンピック開催都市を決める投票はデンマークの首都コペンハーゲンで行われた。勝ったのはリオデジャネイロ、東京は惨敗だった。すべてが初めての経験の中、不眠不休で仕事を続けた髙谷は、投票の結果発表直後、ホテルの椅子で4時間ほどの眠りに落ちた。その後ホテルを出て誰かに会いに行ったが、それがいったい誰だったのか記憶にない。髙谷には選挙の結果はショックだったが、と同時に、翌日には同僚の一人と昼食をとりながら、もう1回やれば勝てるよね、というような話をしていた記憶もある。

長年IOCと深く関わり、この世界のことを熟知している人物の一人、JOC名誉委員(今回の招致活動ではCEOとして全体の指揮に当たった人物でもある)をつとめる水野正人は、この2016年大会の招致活動の敗因をこんなふうに分析する。
「とにかく、リオデジャネイロが強かった。あの当時ブラジル経済は急成長を遂げていたし、IOCの中にも新しい世界でのオリンピック開催という流れもありました。そして何よりも、リオデジャネイロには強烈な熱意というものがありました」
当時リオデジャネイロ招致の陣頭指揮をとっていたカルロス・ヌズマンというブラジルの実力者は、IOCの総会や理事会、あるいはその他にも重要なスポーツイベントがあるたび、宿泊先のホテルのロビーに朝早くから下りてきて、IOCの委員や関係者とにこやかに挨拶を交わし、握手の手を差しのべ、熱意あるロビー活動を繰り広げていた。ブラジルスポーツ界のトップが見せるその姿は、決して通り一遍等の形だけのものではなく、本当にリオデジャネイロはオリンピック・パラリンピックの開催を望んでいるのだということがひしひしと伝わってくるようなものだった。
水野はそんなヌズマンに、あなたの腕は会うたびどんどん長くなっているように見えるよ、と冗談を口にしつつ、同時に、これに比べると日本は劣っているのではないか、と感じていたという。
「結局のところIOCの委員だって人間ですからね。もちろんそれぞれの理事には様々な思惑があり、様々な背景はありますけれど、やはり最後は真心で動くものだと、私は思うんです」
オリンピック・パラリンピックを一つの商品として見れば、東京が提示する2020年オリンピック・パラリンピックは他都市のそれと比べてもまったく遜色のないものだった。いやむしろ、安全面、宿泊面、交通面、それらに関しては間違いなく最高峰のレベルにあった。
であるからこそ、戦略広報部としてはなんとしても、国内支持率を上げ、東京で開催する意義と意味を明確にし、優れたプレゼンテーションを用意し、国内外のメディアにポジティブなニュースを発信し続けなければならなかった。100人余りのIOC委員の一人でも多くになんらかの方法で訴えかけなければならなかった。彼らの意識の中で東京に投票する理由を増やし、東京に投票しない理由を減らし、なぜ2020年は東京でなければならないのか、を強烈にアピールしてゆかなければならなかった。
2012年4月、それまでは髙谷がほぼ一人で切り盛りしてきた戦略広報部は本格的に始動し始める。2016年招致を経験し、いったい何が足りなかったのか、をすでに知っていた髙谷は、人事の構成も含めて上層部にレポートを提出していた。彼に人事の決定権はないが、戦略広報部はスポーツマインドにあふれた人々で構成されるべきだという確固たる確信が髙谷にはあった。同時に彼はこれから先、すでに決定されているIOCのイベントにあわせて、時系列的に、ここはこうする、ここはこうする、という具体的な月ごとの計画表を予算も含めて作成していた。
前回はまったく初めての体験であったがゆえに、コンサルタントのアドバイス通りに動いただけだった。しかし今回は明確な意志を持って、IOCに対してのプレゼンテーションも、誰が、どの機会に、どういうふうに働きかけてゆくべきか、をイメージすることができていたのだ。
<次のページへ続く>
「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる