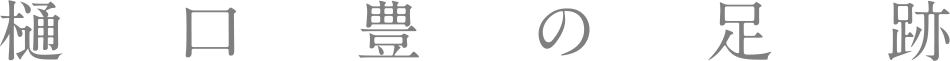スポーツチャレンジ賞

樋口豊は身体の弱い子どもだった。
小学校1年生のときに小児ぜんそくを患い、担当医からは、6年生までもてばいいでしょう、と診断された。
崖下に京浜東北線が走る、北区東十条の高台にあった家の小さな裏庭で、樋口はいつも一人ひなたぼっこをして時間を過ごしていた。だから、彼には低学年の頃学校に通った記憶がほとんどない。
幸いなことに、主治医の診断は外れ、樋口の肉体はひとつ春を迎えるごと、少しずつこの世界を生きてゆく力を蓄えていった。
小学校3年生に上がる頃には、ようやく学校にも通えるようになった。
スケートという魔法
初めてアイススケート場へ行った日を、樋口は今でも覚えている。それは1959年1月15日、小学校4年生で迎えた成人の日だった。
その日彼は家族と共に、水道橋駅のすぐそばにある後楽園アイスパレスに出かけた。白い楕円形のリンクの上にはたくさんの人がいて、冷たい空気の中を軽快な洋楽が流れていた。少し緊張したが、なんだか幸せな気分だった。
受付でずっしりと重いシューズを貸してもらうと、紐の結び方すらよくわからないその奇妙な革製の靴に、樋口は小さな両足を差し入れた。
手すりにつかまり、おそるおそる白い氷の上に乗る。足首と膝ががくがくと揺れる。樋口は勇気を出して手すりから手を離し、一歩足を前に出そうとした。どすん。一歩目で早くも転んだ。なんとか立ち上がって、また一歩足を前に出そうとした。どすん。また転んだ。
何度も何度も転ぶうちに、ほんの数メートルに過ぎないが、ときどき樋口の細く華奢な身体が銀色に光る細いエッジとシンクロし、氷の上をスムーズに移動していくことがあった。滑る、その不思議で快い魔法のような感覚は、一瞬のうちに樋口の心と身体を捉えた。
<次のページへ続く>
「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる