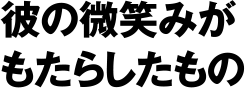スポーツチャレンジ賞

近藤篤 = 写真・文
Text&Photograph by Atsushi Kondo
フィギュアスケートという競技を初めて見たのは、1972年の2月に札幌で開催された冬季オリンピックのテレビ中継だったと記憶している。
瀬戸内海沿岸の田舎町に住んでいた僕にとっては、フィギュアスケートだけでなく、スピードスケートも、ジャンプも、ボブスレーも、バイアスロンも、自分の生きている世界からはとても遠いところにあるスポーツだった。雪と氷の上が舞台、画面に映し出される光景がやたらと白かったことと、みんなが毛糸の帽子をかぶり、分厚い手袋をしていたことが印象に残っている。なにせ僕の田舎ではまだ冬でも小学生は半ズボンで過ごしていた時代だったのだ。
札幌五輪のフィギュアスケートでは、ジャネット・リンという米国の美しい女性スケーターが話題を独占した。
彼女はフリープログラムの演技中に一度尻もちをついてしまったが、最後まで微笑みを絶やすことなく滑り続け、その愛くるしい姿は日本中を、あるいは世界中を魅了した。たぶん他にもたくさんのフィギュアスケーターがいて、素晴らしい演技を見せていたのだろうが(だってオリンピックだ)、僕は彼女の名前しか覚えていない。
樋口豊氏は、その札幌、そしてさらにその4年前のグルノーブルで開催された冬季五輪に、フィギュアスケートの日本代表選手として参加している。
1968年のグルノーブル五輪に向かった時、彼はまだ17歳で、東京の高校2年生だった。初めての五輪、初めての海外、さぞかし感動的な旅だったんでしょうね、と質問すると、樋口氏はニコニコ笑いながらこう答えた。実は、あまりよく覚えていないんですよ。きっとひたすら滑ることに集中していて、周りの景色なんかほとんど見ていなかったのだろう。
とは言え、樋口氏はグルノーブル五輪で海外のトップスケーターたちの滑りに大いに刺激を受け、帰国後すぐにトロント留学へと出かける。まだ1ドルが360円で、海外へ持ち出せるドルにも制限があり、闇ドルなんてものを買わなければならなかった時代だ。1968年のカナダへ行くなんて、大変な決断をしたものだと思うが、それについても樋口本人はあっさりと、だって上手くなりたかったですからね、と答える。
留学期間は3年半、彼はイギリス人のお年寄りの家にホームステイし、朝から晩までひたすらフィギュアスケートの練習に打ち込んだ。トロントで学んだのは「美しく滑ること」、そして「フィギュアスケートとはなによりもまず芸術性を競うスポーツであること」だった。

あれからほぼ45年が経つ。樋口氏が現役で滑っていた頃とは異なり、日本のフィギュアスケートは飛躍的な進歩を遂げ、男女ともに世界の強豪国のひとつとなった。国内で国際大会が開催されれば会場は満員のギャラリーであふれ返り、海外で開催される国際大会では、リンクの周りを日本の企業広告が囲む。スケート教室には受け入れきれないほどの数の子どもたちが通い、リンクの周りには熱心な保護者たちの姿がある。
日本フィギュアスケートの開国への多大な貢献、それが今回樋口氏が功労賞を受賞した理由だ。
長野での冬季五輪開催が決まり、日本フィギュアスケート界が海外からのコーチや振付師を積極的に受け入れ始めたとき、樋口氏はトロントで培った人脈を活かし、橋渡し的存在を買って出た。一流コーチと一流選手のカップリング。当時のミッションについて、本人は具体的にはあまり多くを語らない。私は私にできるお手伝いをしただけですから。樋口氏はいつものように背筋をすっと伸ばし、静かに微笑みながらいつも同じ答えを繰り返す。もちろんそれは大変な「お手伝い」だったに違いない。
日本のフィギュアスケート界が今の立ち位置にたどり着くために、いったいどれだけの人々が縁の下を動き続け、支え続けたのだろうか。樋口氏を含め、彼らはみな誰もがフィギュアスケートに生涯を捧げた人々だった。
2014年2月、第22回オリンピック冬季競技大会は、ロシアのソチで開催される。華麗にスピンし、大胆にジャンプをし、一度尻もちをつき、それでも微笑み続けながら最後まで美しく華やかに滑り続けることで世界を魅了する、そんな日本人スケーターが現れることを期待したい。
まず美しいスケーティングありき、樋口氏が何度も何度も繰り返すように、フィギュアスケーティングの最大の魅力はやはりそこにあるはずだ。
「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる