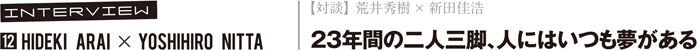スポーツチャレンジ賞

新田佳浩という選手は絶対に金メダルを取れる
YMFS新田選手は長野でのパラリンピックの後、大学は筑波大学に進学されました。在学中に出場したソルトレイク大会では銅メダルでしたが、その4年後、金メダルを期待されていたトリノ大会ではメダルに届きませんでした。一方、荒井さんの方は、詳しくはFOCUSの方に記されていますが、2004年の11月に日本で初めて誕生した障がい者アスリートの実業団チーム、日立システムアンドサービス(現・日立ソリューションズ)「チームアウローラ」の監督に就任されます。そのチームアウローラに新田選手が移籍してきたのは、2006年ですね。

新田本当はトリノで金メダルをとり、そのメダルを祖父の首にかけてあげて、競技者としては引退するはずだったんです。でも転倒してしまって、満足のいく結果を残せませんでした。当時僕はスポーツ用品メーカーに所属していたのですが、同じ環境で続けてもこれ以上の結果は望めないな、という感覚がありました。
荒井このままだと彼はスキーをやめてしまうんじゃないかな、と私は内心心配していたんです。新田佳浩という選手は絶対に金メダルを取れる、それはわかっていましたから、どうしたってやめさせるわけにはいかない。そこで彼に、うちに来て続けないか、と誘いました。もちろん社内で反対というか、懸念する声はありました。いきなりスター選手を引き抜くことになるわけですからね。
新田悩みましたけど、やはり大きな変化を起こすためには、自分の立ち位置を変えようと。それまでは個人として選手活動を続けていましたが、チームアウローラに移ってからは、たくさんの人に支えられている、と同時にたくさんの人のために頑張らなければ、という意識も持てるようになりました。
YMFS確かその頃からですよね、トレーニングがより科学的なものになっていったのは。

荒井はい、そうです。彼が移籍してきた頃から、とにかくデータを取ろう、ということになりました。全てを数値化して、何が足りていて何が足りていないかを理解する。仕事でもスポーツでも、優れた企業や選手はこれをやっています。実際に会社の人がストップウォッチを持って、上りのラップ、下りのラップ、平地でのラップを計測し、それを他の強豪選手のものと比較する、そんな作業を始めてくれました。
新田自分にとっては、何がどのくらい足りないのかを具体的に知ることは、とても役に立ちました。例えば、ある選手に対してタイムが3%劣っているとすれば、身体の全ての部位の強度をそれぞれ3%上げれば、論理的にはその選手に追いつけるわけです。もちろんトレーニングはよりタフにはなります。最初の3ヶ月は、これトレーニング続けて大丈夫なのかな、って心配になるくらい、毎日ものすごい筋肉痛でしたから。
荒井でも、やはり数値は裏切りませんでしたね。結果、彼はバンクーバー大会で金メダルをちゃんととりましたから。あの時の彼はそばで見ていて、神がかっていましたよ。レース前からものすごい集中力で、たぶん僕がそばにいたことすらわかっていなかったと思います。
<次のページへ続く>
「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる