スポーツチャレンジ賞

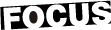
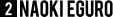
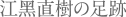
ロンドンへ向けての3年間

世界でさらに上を目指すためにはフィジカルを鍛えなければならない。パワーアップ、それがキーワードだったことは間違いない。しかしながら、身体作りに重きを置き過ぎた分、技術面の強化がおろそかになってしまった。
2006年以降、日本代表は以前ほど勝てなくなり、江黑は監督の座を解かれてしまう。監督を解任されたときはもちろんショックだったが、これは決してマイナスではないのだ、と江黑は考えた。彼と一緒に組んでいた人間が上に上がり、江黑はすこし離れた場所からゴールボールをもう一度見つめることができた。
7位に終った北京五輪の翌年、2009年、江黑はふたたび女子代表チームの監督の座に復帰する。ゴールボールの競技レベルは4年間で驚くほど上がっており、中でも中国の強さは際立っていた。
北京での経験を経て、次の4年間で攻撃力をアップすることを決めた。メンバーを変えない方がディフェンスは安定するが、そのままではチームがぬるま湯につかった状態になりかねない。刺激を与える意味も込め、江黑は若い選手たちをユースから引き上げ、チームを再構築し始めた。
チーム内に競争を持ち込むことで、我々はリハビリスポーツをやっているのではなく、勝つための競技スポーツをやっているんだ、とみんなに意識してもらいたかった。
江黑が一番苦労したのは、女子ゴールボールの世界の選手層の薄さだった。トレーニングはいつも10人前後、選手数が少ないので選手同士の競争がなかなか生まれない。
盲学校のクラブ活動としてこの競技を知り、海外に行けるとか、全日本に入れるとか、そんな一面に魅力を感じて集まってくる選手もいた。一度海外に行くとやめてしまう選手もいたし、厳しく叱責すると、そんなに言われるのならやめます、と下を向く選手もいた。
加えて、彼女たちには子どもの頃から競技歴というものがほとんどなく、誰かと競い合った経験がなかった。だから、江黑が選手同士の競争を意識させようとしても、当の本人たちはどうしていいのかわからない。
この問題を、江黑は話すこと、コミュニケーションをとること、で解決しようと試みた。江黑本人の言葉を借りるなら、「視覚障害者には、言葉にすることが苦手な子が多い」。なぜなら、黙っていても周りがやってくれるから。
たとえば目の前にコップがある。水を飲みたいけれど、コップの中に水はない。彼女たちが置かれた環境では、水をくださいと言う前に、誰かが水をコップに注いでくれる。
同じようなことが、ゴールボールの世界でも起こる。パスをした方が有利な状況にもかかわらず、パスをください、と言われなければ、自分で投げてしまったり、次は私の番だと勝手に思い込み、何も言わずにパスを待っていたり。あるいは、疲れているから私の代わりにボールを投げてください、と言葉にできないがために、自分でボールを投げてハイボールの反則を犯してしまったり。
もっともっと仲間意識を植え付けていきたいんです、と江黑は力説する。選手同士がつながって情報を言葉にして流し合えれば、お互いに刺激し合える。わたしはこれを10回やったよ、じゃあわたしは20回やる。
運動選手はいろいろなことを目で見て学ぶが、視覚障害者は自分の体験でしか学べない。他の選手のプレーを目で見て読み取ることができない分、彼女たちの向上にとって、考えや行動を言葉に置き換えることはさらに重要になってくる。
とにかく話せ、伝えろ、こうなんだろうと勝手に思い込むな。
江黑は3年間ひたすらそれを言い続けた.結果、無口だった選手たちも少しずつ、話し、伝え、主張し、そして競い合うようになっていった。
<次のページへ続く>
「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる






