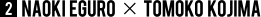スポーツチャレンジ賞
もっと気持ちを伝え合う時間を多く持たないと

小島そういう生徒さんを実際に競技としてのスポーツの世界に引き込む大変さは想像もつかないのですが。
江黑私自身は大変だったとは思わないけれど、選手たちは大変だったんじゃないかな(笑)。
小島ロンドンパラリンピックで金メダルを獲って、ゴールボールという競技がすごく注目されたと思いますが、競技人口は多いのですか?
江黑いえ、競技人口はまだ少ないですね。全体でも50人くらいですよ。
小島少ないんですね。
江黑少ないです。なので、選手間の競争がないんです。一番の問題は、知らないことだと思うんですよ。
小島「知らないこと」?
江黑競技の世界、誰かと競い合うっていうこと自体を知らないんですね。視覚障害者の子どもたちは基本的に自分から何かを発することが少ないんですよ。自分の意思や希望を表現しなくても、全部周りがやってくれることが多い。それに加えて、全く運動をしていなかった子たちをこういう世界に引き込んでいるので、その大変さはあります。今では、選手たちもかなり変わってきましたが、初めの頃は自主性や気持ちを伝える、という部分でとても苦労しました。
小島自主性ですか。
江黑自ら事を起こしていくということは、ゴールボールだけではなく、必要なこと、当たり前の姿だと思います。勉強だって自分がやりたいからやる。嫌々やっても身にはつきませんからね。

小島先生が今おっしゃっていることは、健常・障害っていう線を引かなくても、ごく当たり前のことですよね。
江黑私は視覚障害者の方とある程度長い時間を一緒に過ごしているのですが、「彼らは視覚障害だから」という意識はそれほど持っていないんです。もちろんできないことに関してはお手伝いするけれど、それ以外のことに関しては特にそこまで気を遣っていません。選手たちによく言うのですが、コートの中で挨拶をすることについても、選手の側から、視覚障害者の側から挨拶することだって当たり前のことだと思っているんです。
小島なるほど。
江黑でも面白いのは、「普通はこうじゃないの?」というような表現を私が使うと、怒る選手もいるんですよね。「先生の普通と私の普通は違う」って。普通談義に花が咲くっていうか(笑)。
小島普通にも種類があるんですね(笑)。
江黑視覚障害の方は、ひとりでいる時間の過ごし方が上手いんですよ。家でずっと音楽や朗読を聴いたりね。彼女たちが置かれた環境上、それは仕方ないことだと思うんです。ただ私は、もう少し人に興味を持ってもらいたいんです。普段の生活でコミュニケーションがとれないと、コートに入っても遠慮が出てしまう。そのためにも、もっと気持ちを伝え合う時間を多く持たないといけないと思いながら、合宿などに取り組んでいます。
<次のページへ続く>
「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる