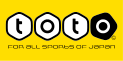セーリング・チャレンジカップ IN 浜名湖
平成27年・第23回 レースレポート(総括)
全国36クラブから集まった102隻・147人のジュニア/ユース世代が熱戦を展開


公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団(YMFS)では、3月27日(金)から29日(日)の3日間にわたり、静岡県立三ヶ日青年の家(浜松市)において「第23回YMFSセーリング・チャレンジカップIN 浜名湖」を開催しました。今大会は全国36クラブから集まった102隻・147人のジュニア/ユース選手が出場しました。
「セーリング・チャレンジカップ IN 浜名湖」は、小学生から高校生までのジュニア/ユース年代における国内最高峰のセーリング大会として、毎年、春休みにあたる3月下旬に開催しています。 大会期間中には、ロンドン五輪レーザー級担当コーチの佐々木共之氏と、日本レーザークラス協会強化委員会の榮樂洋光氏による海上指導やレース後の勉強会、さらには日本オリンピック委員会(JOC)専任メディカルスタッフであり日本セーリング連盟(JSAF)オリンピック委員会トレーナーの江口典秀氏を招き、「ジュニア/ユース世代に必要な身体づくり」や「セーリング選手のトレーニング方法」等の指導を実施しました。
| 期間 | 2015年3月27・28・29日 |
|---|---|
| 会場 | 静岡県立三ヶ日青年の家(静岡県浜松市) |
| 共同主催 | 公益財団法人ヤマハ発動機スポーツ振興財団、NPO法人静岡県セーリング連盟 |
| 参加艇 | OP級:32艇、ミニホッパー級:8艇、レーザー4.7級:17艇、FJ級:13艇、420級:32艇 |
新種目2クラスが採用され、全5種目の大会となる
ヤマハ発動機株式会社が主催する「ジュニアチャンピオンレガッタ」の第1回大会が開催されたのが、今から22年前の1993年。当時はまだ、セーリング競技においてはジュニア世代の技術向上という概念が今ほど一般的ではなく、国内最大のヨットビルダーであったヤマハ発動機が、自社製品の一人乗りディンギーを種目とし、ジュニア世代の技術向上を目的としたレガッタを創設したところに、この大会の歴史は始まりました。
その後、2008年からは主催者が、公益財団法人であるヤマハ発動機スポーツ振興財団(YMFS)に移管されたことで、インターハイ種目であるFJ級や世界で最も普及しているジュニア対象ディンギーであるOP級などのヤマハ発動機の製品以外のクラスが種目として採用され始めました。そしてジュニアチャンピオンレガッタから数えて第23回目となる今大会では、新種目として一人乗りのレーザー4.7級と二人乗りの420級の2クラスが採用されることになり、種目数5クラスという陣容を誇るレガッタとして生まれ変わりました。
参加艇数もOP級32艇、ミニホッパー級8艇、レーザー4.7級17艇、FJ級13艇、420級32艇の合計102艇と昨年比で24艇増、参加人数も147人とこちらも昨年比で44人増となりました。この背景に、新種目として採用された420級が、今年からインターハイの種目として採用されることに加え、この大会が420級とレーザー4.7級の世界選手権への派遣選手選考対象レースに指定されたことが大きく影響したと考えられます。
もちろん、本大会の主旨である、ジュニア/ユース世代の技術向上と普及という理念に変わりはなく、今年もオリンピックセーラーなどを招いてのレクチャーも並行して実施され、毎日レース後には国内一流の講師による勉強会が行われました。
風速6〜7m/sの絶好のコンディション
北西の季節風が吹くことで知られるこの季節の浜名湖。例年、ヨットが出航できないほどの強風が吹き荒れることのあるこの大会ですが、今年は初日と2日目に風速6〜7m/sというディンギーセーリングには絶好のコンディションとなり、この2日間でOP級を除く4クラスで全7レースが消化されました(OP級は6レース)。最終日は残念ながら無風のため全レースがキャンセルされましたが、絶好のコンディションで7レースが消化されたことで、各選手ともその実力を余すところなく発揮し、その結果がレース成績にきちんと反映された大会となったようです。
唯一のヤマハ製ディンギーのクラスとなったミニホッパー級(現在は製造されていない)には山梨県の山中湖中学ヨット部から6艇、神奈川県の逗子開成中学ヨット部から2艇がエントリーしました。セール面積が小さく、艇のコントロールが容易なこのクラスには、ヨットを始めて1年足らずの初心者が多く、初参加で優勝した逗子開成中学ヨット部の大野達也選手も、昨年の秋からヨットを始めたばかりの選手。波のない浜名湖ですが「こんなに風が強くて、波が高い日に乗ったのは初めてです」(大野選手)と言うほど。
大会種目に採用された2012年大会から3大会連続で女子選手が優勝しているOP級ですが、今大会も女子選手の活躍が目立ち、なんと1〜4位まですべて女子選手が名を連ね、表彰台を独占する結果となり、女子選手による連続優勝記録は4に伸びました。優勝した坂井友里愛選手(江東区立深川第五中学校2年)は、江東区から東京オリンピックに選手を送り込むことを目的に山崎孝明江東区長が主導して設立された「江東区立小中学校セーリング部」に所属して、東京五輪セーリング競技の会場として予定されている若洲ヨット訓練所で毎週末練習している選手です。「セーリングの練習は週末だけで、平日は中学校の軟式テニス部で活動しています」という坂井選手は、5年後にオリンピックの舞台に立っているのでしょうか?
第1回大会から昨年大会まで22年にわたって本大会の中核種目として採用されてきたシーホッパー級SRに代わる形で採用された一人乗りの新種目がレーザー4.7級。シーホッパー級SRよりセール面積が小さいことから、中学校高学年〜高校低学年の選手がエントリーしました。上位グループでは世界を目指す選手たちによる高いレベルのレースが展開され、東海大付属高輪高校1年の池田樹理選手と市原市立ちはら台西中学校3年の菅沼汐音選手が大接戦を繰り広げた結果、同ポイントながら池田選手が優勝を勝ち取りました。
OP級と並び、今大会最多となる32艇がエントリーした新種目の420級。今年のインターハイから新種目として採用されることもあり、東日本を中心にインターハイの常連校など15クラブが参戦しました。上位争いは3艇エントリーした慶應義塾高校が上位を独占。7レース全てのトップフィニッシュを慶應の3艇が独占し、さらに4レースで1・2・3フィニッシュを決めるなど突出したチーム力を見せつけました。その3艇の中でも抜きんでた実力を発揮したのが高宮豪太/樫本達真チームで、7レース中5レースでトップフィニッシュするというダントツのリザルトで初代チャンピオンの座を獲得。「インターハイには420級で出るか、FJ級で出るかは決まっていませんが、希望としては新種目の420級で出場したいと考えています」(高宮選手)。
同じ2人乗り種目である420級に比べるとエントリー数も13艇と少なく、レベル的にも高校からセーリング競技を始めた中級程度のチームがエントリーしたFJ級ですが、優勝した佐久間航/中村純也(稲毛高校ヨット部)は7レース中6レースで1位、2位となった第6レースがカットとなるダントツのリザルトを残しました。練習場所は千葉県立稲毛ヨットハーバー。「同じハーバーで強豪の磯辺高校ヨット部が活動していて、いっしょに練習させてもらうこともあって、大いに勉強になります」(佐久間選手)。
順位よりも、技術向上を目的としたレガッタ
新種目となるレーザー4.7級と420級では、今年の世界選手権への派遣選手選考基準となった今大会ですが、大会の主旨はあくまでもジュニア/ユース世代のセーラーたちの技術向上が目的です。レガッタの順位だけに一喜一憂するのではなく、この大会に参加することでどれだけセーラーとしての力量をアップすることができるかが、本大会のアイデンティティです。
例年どおり、今年もオリンピックセーラーなど一流のアスリートを招いてのレクチャーが行われました。今大会はアトランタ五輪にレーザー級代表として、シドニー五輪に49er級代表として2大会のオリンピックに出場した佐々木共之さん、鹿屋体育大学助教で鹿屋体育大学ヨット部監督兼部長の榮樂洋光さん、昨年に引き続きJSAF(日本セーリング連盟)オリンピック委員会トレーナーとしてアテネ五輪、ロンドン五輪でセーリングチームを担当された江口典秀さんの三人が招かれました。
初日の勉強会は江口トレーナーによる、セーリングのためのトレーニング講座。選手時代はスキーのアルペン競技のアスリートとして活動し、その後もアルペン競技のトレーナーとして独立。「アルペン競技とセーリング競技は、いかにバランスを取るかという点で共通点が多く、スキーのシーズンオフとなる夏場のトレーニングとしてボードセーリングなどのセーリング競技に取り組む選手も多いんです」(江口さん)。勉強会にはバランスボードやバランスディスクなどが持ち込まれ、バランスを正確に取るための正しい姿勢などについて詳細なレクチャーが行われました。2日目は海上で撮影した動画をもとに、一人乗り種目は佐々木さんが、二人乗り種目は榮樂さんが勉強会を実施。中〜強風が多かったことから、バングやカニンガムを使ったデパワーの手法について動画の実例をもとに解説されました。また、海上ではインフレータブルボートに乗った2人のコーチが、レースの合間に直接指導を行い、ウィークポイントを指摘された選手は次のレースで見事に修正して順位を上げるという場面も見られました。
2012年の第20回大会から始まった、ハンディGPS端末によるレース解析は今大会も継続して行われました。レース艇にハンディGPS端末を搭載し、その日に行われたレースの功績をプロット、レース終了後に回収した端末からデータを集積し、ヨットレース再現アプリケーションの上で走らせることでレースの鳥瞰図をモニターに再現して、ヨットレースの戦略を検証する試みです。一度に全種目に搭載するほどの端末が用意できないので、レース毎に搭載するクラスを選んでの実施となりましたが、ここで集められたデータは保存され、今後の研究に活かされることになります。
時代に合わせて変容するレガッタ
日本のヨットレース、特にジュニアやユース世代が取り組むディンギーレースは、国体やインターハイにどういった種目が採用されるかで、その勢力図が大きく変化するという特徴があります。
冒頭で述べたように、当初はヨットビルダーであったヤマハ発動機株式会社が、自社製品のヨットを種目としてジュニアの育成を目的に始まった本大会ですが、ヤマハ発動機がデザイン、建造を行ったシーホッパー級SRが国体セーリング競技の少年種目として採用されたことで、参加艇数を大きく伸ばしてきたという経緯があります。
ところが、今年の和歌山大会から国体の少年一人乗り種目がシーホッパー級SRからレーザーラジアル級に変更され、インターハイのフォーマットがFJ級1種目からFJ級と420級の2種目へと変更されるなど、ジュニア/ユース世代の勢力図がガラリと変わることになりました。
こうした大きな変更に併せていく形で、本大会の種目もドラスティックに変更されることになりました。ヤマハ発動機というひとつのメーカーが主催するという形で始まった本大会ですが、7年前から公益財団法人であるYMFSへと主催が移管されたことで、日本のセーリング界全体を見渡した貢献が要求される大会となったという歴史的経緯が、今回の種目変更の背景にあります。
ただ、本大会が目指してきた、ジュニア/ユース世代の技術向上やセーリング競技の普及といった目的に変わりはなく、また「セーリングを通した心身ともに健全な子どもたちの育成」というYMFSの理念に基づき、どのような種目が採用されることになっても、多くのジュニア/ユース世代のセーラーたちに支持されるレガッタとして存在し続けることが、日本のセーリング界全体に貢献する道筋であると確信します。
大会の様子
上位成績
OP級(参加32艇)
| 1位 | 坂井友里愛 | 江東区立小中学校セーリング部 |
|---|---|---|
| 2位 | 三浦凪砂 | 静岡県セーリング連盟浜名湖ジュニアクラブ |
| 3位 | 谷口美羽 | 江東区立小中学校セーリング部 |
ミニホッパー級(参加8艇)
| 1位 | 大野達也 | YMFSジュニアヨットスクール葉山 |
|---|---|---|
| 2位 | 権正一輝 | 山中湖中学校ヨット部 |
| 3位 | 高村彪太朗 | 山中湖中学校ヨット部 |
レーザー4.7級(参加17艇)
| 1位 | 池田樹理 | ユースチーム東京 |
|---|---|---|
| 2位 | 菅沼汐音 | 千葉ヨットビルダーズクラブジュニア |
| 3位 | 大久保諒 | 神奈川ユースヨットクラブ |
420級(参加32艇)
| 1位 | 高宮豪太/樫本達真 | 慶應義塾高校ヨット部 |
|---|---|---|
| 2位 | 柳内航平/倉内凱吾 | 慶應義塾高校ヨット部 |
| 3位 | 吉村彰人/久保田空 | 慶應義塾高校ヨット部 |
| 女子優勝 | 花井静亜/市井菜月 | 岐阜県立海津明誠高校ヨット部 |
※写真は各クラスの総合優勝と女子優勝者
FJ級(参加13艇)
| 1位 | 佐久間航/中村純也 | 千葉市立稲毛高校ヨット部 |
|---|---|---|
| 2位 | 遠藤優太/真田篤 | 静岡県立相良高校ヨット部 |
| 3位 | 田中聡馬/石崎渉太 | 岐阜県立海津明誠高校ヨット部 |
| 女子優勝 | 山田雅/榑林沙樹 | 静岡県立相良高校ヨット部 |
※写真は各クラスの総合優勝と女子優勝者
第23回「セーリング・チャレンジカップ IN 浜名湖」は、
スポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。