スポーツチャレンジ賞

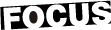
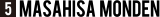
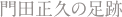
アテネ、その後

あのアテネから11年が経つ。
結果から言うと、代打のつもりだった門田は、アテネ以後、レギュラーとして障がい者スポーツの世界に定着。トレーナーの存在意義を積極的に説き、且つその組織化に尽力することになる。パラリンピック帯同のトレーナーは北京では2人に増え、ロンドンでは3人に増えた(おかげでロンドンでは、フィジカルトレーニングを指導してきたゴールボール女子チームの優勝をコートサイドで祝うことが出来た)。
2007年にカリキュラムを作成し始め、2008年にスタートさせた障がい者スポーツのための障がい者スポーツトレーナー登録制度も、今年で7期目を迎え、全国でほぼ100人の登録者がいる。

次に整備すべきは競技団体付のトレーナーの拡充と、エリアごとのミーティング制度だ。団体ごとに存在するトレーナー数はたしかに増えてはきているが、今後はよりチームとしてトレーナーが選手サポートに貢献できる環境つくりが必要となる。
「九州、中四国、関西、北陸、東北、と言った具合に、エリアごとにリーダーを作って、地域の中での協力体制を整えたいんです。選手が困っているとき、そのエリアのリーダーに連絡を取れば、近くのトレーナーがなんらかの解決策を示してあげられる、といった具合に」
2020年の東京五輪まではそれぞれの地域で使える予算もある。でもそのあとは、はい、おつかれさまでした、となるかもしれない。ならば、それまでにシステムは作り上げておかなければならない、というのが門田の考えだ。今は追い風が吹いている。その風を利用しない手はない。

来年、第15回パラリンピックはブラジルのリオデジャネイロで開催される。でも、そこにはもう自分の姿はないですよ、と門田は言う。もうすでに若い仲間の一人には、次は君が行くんだ、と伝えている。君の世界で君のネットワークを作れよ、と。
「実際、自分の体力的にも、パラリンピックであの作業をこなすのは現実的じゃないですよね。東京のとき、僕は56歳になっています。午前4時に選手からチョンチョンってつつき起こされて、マッサージしてくださいって言われたら、さすがに、お前、俺の何倍若いんだよ、ってなりますもん」
そして2020年は、できれば観客席から日本選手団の活躍を眺めていたいと、門田は希望している。
「そうなれば、やっとゆっくり見られるじゃないですか、ああパラリンピックってこんなふうにやってんだなあ、って」
<了>
「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる






