スポーツチャレンジ賞

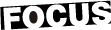
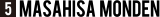
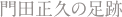
理学療法士であるからこそ
2000年の春先だった。門田は広島市の障がい者スポーツセンターで指導員をしていた人物から、唐突なオファーを受ける。当時、門田は15年間務めた朋和会を辞し、今現在彼が所属する飛翔会グループへ身を移してまだ間もなかった。
「その人は日本車いすテニス協会の理事をしていた方なんですが、その年のチームカップに参加する日本チームのトレーナーをやってみないか、って誘われたんです」
シドニーパラリンピックを数ヶ月後に控え、協会ではこの大会を非常に大切なものと位置づけていた。参加するスポーツから勝つためのスポーツへ、障がい者スポーツの世界は大きく変化し始めていた。トレーナー帯同の必要性、協会はその点を見極めたがっていた。
障がい者スポーツのチーム帯同トレーナー。門田にとっては初めての経験であったが、特に断る理由も尻込みする理由もなかった。選手のパフォーマンスを最大限に引き出すためのケアは、彼が長いキャリアの中でいつもやってきたことだ。
「ところが、でしたね。これまでの自分の仕事なら、試合のことだけを考えていれば良かったんです。でも、あの時はちょっと勝手が異なりました」
ケアすべき選手は9人、テニスは個人競技なので、選手によって試合時間も異なる。各選手の時間調整は難しかったが、門田にとっては、試合以外で選手の肉体にかかる負荷やストレスの方が気になった。
「たとえば、車いすテニスの選手たちは石畳や砂利道を、試合会場まで自分の腕で車輪を回して移動するわけです。ということは、試合が始まれば腕として使うべき肉体器官を、移動中は脚として使わなければならない。ハードな移動はせっかく調整した筋肉に微妙な疲れやストレスをもたらしてしまいますよね」

宿舎に戻れば戻ったで、慣れないホテルでの生活が待っている。試合後にほぐしたはずの筋肉も、トイレで、あるいはバスルームで、再び酷使されることになる。
そこには門田の知らなかったこと、気づいていなかったがたくさんあった。でも同時に、理学療法士の勉強をしてきた自分だからこそ、気がつくこともあった。
「彼らがどんなふうに、どの筋肉を使ってトイレの便座に移るかなんて、健常者相手のトレーナーではわからないですよね」
障がい者スポーツに関わる人間は、本当にすべてを理解していなければならないことを、門田はこの大会で深く認識する。
<次のページへ続く>
「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる






