
1985年9月2日, 中島正太は東京都葛飾区で生まれた。
葛飾ラグビースクールに入団したのは5歳の時だ。父も母も熱心なラグビーファン、その影響で彼もラグビーを始めた、いや始めさせられたといったほうがより適切だろうか。練習場は、柴又帝釈天のちょうど裏手、荒川の河川敷にあり、毎週末中島はラグビージャージに着替えてそのグラウンドに通った。
「でも本音を言うと、小学校時代の僕は、ラグビーよりも野球が好きでした。当時住んでいたマンションの裏手には神社があって、境内で毎日のように草野球をやっていた。ラグビーは土日にやるもの、と割り切っていた感じです」
中学に上がる年、父親は仕事の関係で、自身の生まれ故郷である埼玉県熊谷市に戻ることを選択する。中島は新しい土地で新しい仲間と新しい生活を始めることとなった。<正太、お前はどうしたいんだ?>と父は息子に聞いた。<部活動で知り合った仲間も大事になるぞ>。
本当は野球選手になりたかったが、遊び程度の草野球しかやってこなかった自分が、リトルリーグで鍛え上げてきた仲間に敵うとは思えなかった。バスケもやりたかったが、活躍するには身長が足りない気がした。結局、小学校時代ずっと続けたラグビーを選ぶしかなかった。
中島は熊谷東中学校に入学し、ラグビー部での日々をスタートさせる。雨でも、雪でも 朝から晩まで、ずっと体を鍛え続けた。運動場が使えなければ、体育館でリアルなタックルに明け暮れた。トレーニングはきつかったが、気がつくと、いつの間にかラグビーにのめり込んでいた。
ラグビーにとことん打ち込んだ中学生時代、全ては概ね順調に進んでいった。新人戦の東日本大会では準優勝を果たし、キャプテンを務めた3年時には関東大会で3位にも入った。自身も埼玉県選抜の一員として、花園でプレーした。
中学校を卒業すると、中島はラグビーの名門熊谷工業高校へと進学する。ほかにも選択肢は何校かあったが、埼玉県選抜の仲間と、熊工に行って全国大会を目指そう、という話はしていたし、熊谷出身の父も、できれば熊谷工業に行って欲しいと願っていた。
しかし、今から思えばその選択は挫折の始まりだったのかもしれない、と中島は熊工での三年間を回顧する。
「小学校からラグビーを習っていた分、中学生の時は全てがうまく運びました。でもそのノリで高校に進んでしまって、僕は努力を怠ったのかもしれません。一応試合には出られましたが、周りの仲間が中学時代の悔しさを糧に高校日本代表に選ばれたりする中、僕は結局伸びきれず、埼玉県選抜止まりでした」
<次のページへ続く>

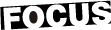
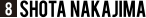
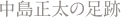
「その仕事、やりたいです」

大学は筑波大学体育専門学群に進んだ。社会人になってさらに上のレベルでやっていけるとは思えなかった中島は、プレーヤーとしてラグビーをプレーするのは大学まで、そう心に決めていた。
「栄養についても、ウェイトトレーニングも、これまでとは違った視点で見つめるようになったし、それを学べる環境が大学にはありました。この四年間が最後の時間、そう考えると日頃のトレーニングにも高校時代以上に真剣に打ち込むことができましたね」
ポジションはスタンドオフ、足が特別速いわけでもなく、フィジカルが強かったわけでもなかったが、中島は仲間の強みを生かせる賢い選手だった。二年生の時はほぼ全ての試合に出場、三年生の時は一度レギュラーポジションを失ったが、最終学年では副キャプテンとして全試合に出場した。
ラグビーをやりきったら、卒業後は体育の教師になり、ラグビーの指導者をやりたい。中島はそんな未来像を描き、実際に教職課程も履修していた。しかしラグビーの神様は、彼の人生の向かう先をほんの少しだけ変える。
大学4年の12月、最後の大学選手権が終わった翌日だった。ちょっと監督室に顔を出してくれないか。中島は監督の古川拓生から声をかけられる。
「セコムラガッツにアナリストの仕事があるそうだ。君に向いていると思うんだが、どうだろうか」
トップリーグ所属ではなかったが、当時セコムはラグビー部の強化に力を入れているチームのひとつだった。陣頭指揮をとっていた人物は現在日本ラグビーフットボール協会でGMを務め、エディ・ジャパン成功の立役者とされる岩渕健輔だ。
中島はセコムラガッツのチームディレクターを担当していた大村武則(現日本代表チームマネージャー)に連絡をとり、チームが本拠地を置く狭山市に向かった。この時の会話で、中島がはっきりと覚えている大村の台詞がひとつだけある。
「プロの世界だから、君がどんなに頑張っても、もしくはどんなに楽をしても、評価されるのは結果だけ、仕事の過程は関係ない」。
中島は答えた。「その仕事、やりたいです」
大村は当時を思い出しながら、こう語る。

「僕はヤマハ発動機からセコムに移り、岩渕のもとでチーム強化に取り組んでいました。チームは優れた分析担当を必要としていたんですが、海外からいきなり呼んでくるのは難しい。そこで、国内の様々な大学の指導者の方に声をかけていたんです。すると、筑波の古川監督から、いい子が一人いるよ、というお返事をいただいた。我々の仕事で、個人の資質として一番大事なのは、限りなく向上心があることです。しかし一方で、ラグビーはあくまでもチームスポーツですから、私欲が少ない、という人間でもなければならない。実際に会ってみると、正太はすべての面でスペシャルでした。だから、どうしてもこの若者が欲しい、ということになった。説得には時間がかかったような記憶があります。彼自身が教員を目指していたし、トップレベルのチームからアナリストの仕事を依頼されるということを、にわかには信じられなかったかもしれません。
仕事柄もあるんでしょうが、彼は冷静な男です。後の話になりますが、日本代表でエディ・ジョーンズが周囲を怒鳴り倒し、誰もが一度外に出て大きく深呼吸したくなる状況でも、正太は『エディさんまたなんか言ってますね』で済ませていました。かといって、数字とグラフを追いかけている冷たい男かというとそうではなく、孤立気味だったフランス人のスクラムコーチに、『こっちでコーヒー飲みませんか?』といつも声をかけるような心を持っています。エディは彼のことを間違いなく信頼していたし、僕にとっては宝物みたいな男ですよ」
<次のページへ続く>

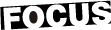
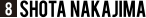
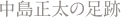
アナリストという仕事
セコムラガッツの現場で働き始める前、中島はまず映像解析のためのソフトウェア、ゲームブレーカーを熟知するところから手をつけた。プロとしてのアナリスト。仕事に不安がなかったわけではないが、中島の強みは、大学でそれに近い作業を体験していたことだった。筑波大学のコーチ陣も同じ映像解析ソフトを使っていたし、彼自身も自分のプレーの参考のために映像の分析作業に打ち込んでいた。卒業論文もそのソフトを駆使して作成したほどだ。
「撮った映像をPCに取り込み、次にそのファイルとゲームブレーカーをリンクさせるんです。このソフトの優れた点は、自分でカスタマイズできるところ。絵の具のパレットのように、自分が得たい情報を仕分けでき、スクラム、タックル、パス、成功したシーンと失敗したシーン、ラグビーの試合中に起こるすべての出来事を、各々のカテゴリーで非常に細かく設定していけるんです」
例えば、一口に「成功したタックル」と言っても、チームによって評価が異なる。日本の場合だと、タックルは低く倒すのが基本だが、アイルランドでは高く入るのが良いとされる。相手を倒さないでモールを作れば、ボールをターンオーバーできる、という発想がアイルランドにはあるからだ。
「同じタックルを日本でやったら、良くないタックルに分類されます。だからアナリストはそれぞれそのチームのパレットを持たなきゃいけない。僕の場合なら、セコムの時のパレット、エディ・ジャパンのパレット、あるいはセブンス(7人制日本代表)のパレット、すべて設定が異なるわけです」
同じラグビーでも、コーチの考えが異なればプレーの分析も異なってくる。
重要なのは、コーチ陣の考えをアナリストがどう捉え、どういうものを提示してゆくか、だった。
中島が入部した翌年、セコムは突然強化の打ち切りを決定し、彼は仕事の場をキヤノンイーグルスに移す。しかし結果的に考えれば、この強化の打ち切りが、中島のキャリアにとっては後々極めて重要なターニングポイントとなった。
中島の能力を高く評価していた岩渕健輔は、セコムを去り、日本協会のゼネラルマネージャーに就任する。2012年、エディ・ジョーンズが日本代表ヘッドコーチの座についたとき、GM岩渕は中島をアナリストとして推薦した。しかし前出の大村によれば、エディはすでにキヤノンでアナリストを務める男の存在に注目していたのだという。
2012年1月、中島の所属するキヤノンイーグルスがエディ率いるサントリーとの練習試合に出かけた際、彼は中島に一言短くこう言った。「よろしくね」
「2000年、エディがACTブランビーズのヘッドコーチを務めていたときから、僕は彼のラグビーが好きでした。ブランビーズはとても攻撃的で、ボールをよく動かし、緻密なラグビーをやっていた。僕自身、現役時代は肉体的に劣っている分、考え、準備をして勝とうとしていましたから、エディのチームには強く興味を惹かれました」
<次のページへ続く>

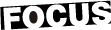
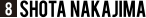
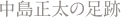
エディ・ジョーンズとの3年半

2012年4月、中島はキヤノンを去り、ジャパンでの日々をスタートする。エディは予想どおり、いや予想をはるかに超えて、極めて優秀で、極めてエキセントリックなコーチだった。
「僕は朝7時頃に起きるんですが、メールを開くと朝4時にはエディからリクエストのメールがもう届いていますからね」
ラグビーの映像の他にも、他のスポーツ、あるいは指導者についての情報やミーティングを、エディは貪欲に欲した。例えば、華麗なパスサッカーで欧州サッカーを席捲したFCバルセロナの試合の映像、あるいは女子バレーや女子サッカー日本代表の監督達とのミーティング、ジャイアンツの原監督を訪れたこともあった。エディは、日本が世界で勝つために必要な強化方法を模索し、自分の手元に集まるデータをいかに活用すべきかを考え、自分のやり方が間違っていないことを確認したがった。
「日本人だからできない、体が小さいからフィジカルの部分では戦えない。これまで日本人自身が不可能だと半ば諦めていたことに対し、彼はいつも、どうしてそういうネガティブなマインドを持つんだ、それは言い訳だ、と厳しく言い続けました。ラグビーはフィジカルからは逃れられない、だからそこも伸ばすんだ。たしかにそこは日本の強みではない、でもそこから目を逸らし続けていたら、ラグビーは戦えないぞ、と」
より高度のパス、より高度の判断、より高度の振る舞いをエディは選手に求めた。午前6時から始まる過酷な4部練習は有名な話になったが、選手だけではなく、エディは代表に関わる全ての人間に、常に完璧な仕事を求め、それはアナリストも例外ではなかった。
「できない、という答えはエディには存在しません。例えば、いつもは会議室でやるミーティングを、彼は突然グラウンドでやりたい、と言い出す。そのとき僕に求められるのは、できないという説明ではなく、別の選択肢です」

スタジアムの大型スクリーンに映像を流せるのか、もしそれが無理ならグラウンドのそばのロッカールームでミーティングをして、すぐに外に出られる環境を整えるのか。プランAがダメなら、プランB、プランCを用意する。理不尽な要求も多かったが、中島はエディ・ジョーンズという極めて難解な(まるで禅問答を繰り返す僧侶のような)監督との仕事を楽しめていた。
「アナリストという仕事は、基本的にはリアクションの仕事です。無理難題であったとしても、いっぱいリクエストをもらえるということは、それを実現するために考える時間やチャンスを与えられるわけです。リクエストをもらえないアナリストは辛いですよ。何のためにデータを取っているのかもわからない、あるいはそれがまったく生かされない。そういう意味では、僕はセコム時代も、キヤノン時代も、エディからも、リクエストはもらえました。彼らは分析に理解があり、アナリストの使い方を心得ている人達だったと思います」
<次のページへ続く>

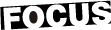
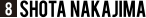
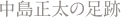
アナリストが見つめた「史上最大の番狂わせ」

2015年9月19日、ブライトン・コミュニティ・スタジアム。その日、中島正太は日本代表スタッフとともに、コーチボックスでワールドカップ初戦、強豪の南アフリカ戦を迎えた。
「緊張ですか? していたといえば、していたかもしれません。でも僕はずっと単年契約で働いてきていたので、どちらかというとW杯までたどり着けた安堵感と達成感の方が大きかったです」
通常のテストマッチと異なっていたのは、エディがいつになくナーバスになっていることぐらいだった。
「あの時僕が考えていたのは、これだけの選手たちが集まって、あれだけのレベルの準備を4年間やってきて、それでもW杯で1勝もできないなら、それは『もう日本はラグビーをするな』ってことなんじゃないだろうか、ということでした」
中島にも、勝てるかどうか、それはもちろん分からなかった。しかしこの3年間、すべきことはもう何もない。それぐらい選手たちはギリギリのところまでやってきていた。
「あの試合は最初から15人全員が良いパフォーマンスを見せていました。タックルも決まっていたし、タックル後の起き上がりも良かった。何より選手たちの表情が落ち着いていたし、用意していたプレーも出せていた」
前半を終えて10-12、日本は予想外の健闘をしている、という程度にしかとらえていなかったゲームは、後半に入っても均衡は崩れない。異様な盛り上がりを見せるスタジアムの一角で、中島はアナリストとして静かに戦況を分析していた。
「残り20分、これが常に日本の課題だったんですが、あの試合ではそこに至ってもチームのパフォーマンスは落ちていなかった。日本はトレーニングの積み重ねを、自信としてグラウンドの上で表現できていました」
後半33分、南アがPGを決め32対29、ゲームは最終章に突入し、試合終了直前、今度は日本が敵陣深い位置でPKのチャンスを得る。エディの狙いはあくまでも引き分けだったが、選手達は南アフリカ相手に勝ちに出た。引き分けで歴史は作れない。スクラム、崩れる、再び組み直してスクラム。
「エディはペットボトルを叩きつけ、ヘッドセットも投げ捨てていました。僕ですか?あえてリスクをとった時の方が、ゲームは良い結果で終わる、そんな感覚はありましたが、日本が南アフリカに勝つという具体的なイメージは浮かばなかったです」
83分55秒、左サイドに走り込んだカーン・ヘスケスがトライを決め、ラグビー史上、いやスポーツ史上最大の番狂わせは完結する。中島の隣では30秒前に激怒していたエディが、満面の笑みで喜んでいた。

<次のページへ続く>

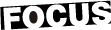
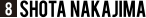
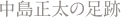

ワールドカップ、そしてリオへ。
予選リーグ3勝1敗。決勝トーナメント進出こそ果たせなかったものの、ジャパンはサモア、アメリカ戦にも勝利し、見事な数字と驚きを残してワールドカップを去ることとなった。
アメリカ戦の夜、中島正太はホテルに戻ると、帰り支度をしながら一人静かに部屋で過ごした。もうなにもしなくていい時間、エディ・ジャパンのアナリストを引き受けてからそんな時間は初めてだった。終わったばかりの試合の分析もせず、テレビ画面を眺めている。なんだか不思議な感覚だった。
「アメリカ戦はある意味で、南アフリカとの試合よりもタフでした。あそこで勝つか負けるかで、我々が残すものの意味合いが大きく異なっていたんです。試合が勝利で終わった時、初めて一つの大きなプロジェクトが完結したような気がしましたね。あの試合まではただひたすら、その日その日を懸命に、大切にやり続けていました。最後にようやくそういう一日一日が全部繋がって、一つの結果になったんです。そのプロジェクトに携われたこと、このチームに関われたことが嬉しかったし、このチームが好きだったなあ、という感情が溢れてきました。」
その6日後、アナリスト中島正太は東芝府中のグランドに向かい、かねてから決まっていた7人制ラグビー日本代表チームの活動に合流する。
そこからさらに10か月後の2016年8月9日、7人制日本代表はリオ五輪の予選リーグ初戦、ニュージーランド代表相手に14-12の大金星を挙げる。惜しくもメダル獲得はならなかったが、史上初のベスト4進出という「もうひとつの快挙」を成し遂げた。
前日本代表キャプテンの広瀬俊朗が、こんなことを語ってくれた。

「南アフリカ戦までの3年半の道のりは、僕たちプレーヤーだけではなく、誰にとってもほんとうに厳しいものだったと思います。それは頂上の見えない山登り、いったい今自分がどこをどこに向かって歩いているのかもわからない、そんな日々の連続でした。でも、気がつくといつの間にか頂上にたどり着いていたんです。正直、神様みたいな存在っているんだな、って思いましたよ。
もちろん、神様だけじゃなくって、たくさんのスタッフが、いつもプレーヤーズファーストでサポートし続けてくれたからこそ、あのW杯があったんです。例えば正太さん、彼が用意してくれた映像を見ることで、僕たちはプレーの質、走りの質を具体的に確認し、改善することができた。正太さんが出してくれた数字を見て、自分たちに何が足りないのかを具体的に把握することができたんです。それぞれの選手が、いつでもデータにアクセスできるよう、1人に1台ずつタブレットを用意してくれたのも彼でした。
勝つために練習はしているけれど、ラグビーというのは相手に勝つことにフォーカスしているわけではないんです。チームに関わる全ての人間が、自分たちにできることを全てやりきった、その向こうに勝利があったんじゃないでしょうか」
<了>
写真・文
近藤篤
ATSUSHI KONDO
1963年1月31日愛媛県今治市生まれ。上智大学外国語学部スペイン語科卒業。大学卒業後南米に渡りサッカーを中心としたスポーツ写真を撮り始める。現在、Numberなど主にスポーツ誌で活躍。写真だけでなく、独特の視点と軽妙な文体によるエッセイ、コラムにも定評がある。スポーツだけでなく芸術・文化全般に造詣が深い。著書に、フォトブック『ボールピープル』(文藝春秋)、フォトブック『木曜日のボール』、写真集『ボールの周辺』、新書『サッカーという名の神様』(いずれもNHK出版)がある。






