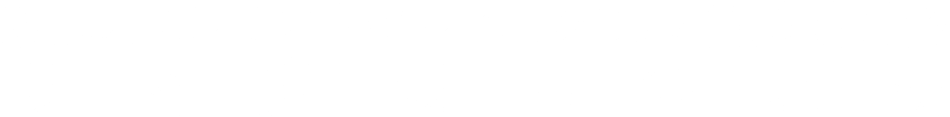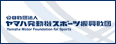第6回 ヤマハ発動機スポーツ振興財団 スポーツチャレンジ賞 奨励賞は、東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会 戦略広報部に贈られることとなった。個人ではなく、ひとつの団体がこの賞を受けたのは今回が初めてのことである。
東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会は2011年の9月に立ち上げられ、事業部、国際部、計画部、総務財務部と共に戦略広報部も活動を開始した。
2016年大会の招致活動での敗北、さらに2011年3月の大震災、この二つは再度の招致活動に深い陰を落としていた。また負けたらどうするのか?という声があり、被災地で困っている人間がいるのにオリンピック・パラリンピックどころではないだろう、という意見もあった。
しかしJOCと東京都は2020年オリンピック・パラリンピックの招致に挑むことを決定する。もちろんそこに逡巡や熟慮がなかったわけではない。JOCの竹田恆和会長は自ら東北三県の知事と会談し、招致の是非を問うた。3人の知事は、オリンピック・パラリンピックはきっと被災地にも、この国にも、希望と勇気を与えるはずだ、と答えてくれた。
とは言え、世間一般の反応はオリンピック・パラリンピック開催に依然として懐疑的だった。2012年5月、オリンピック・パラリンピック開催に対する国内支持率はわずか47%に過ぎなかった。
<次のページへ続く>

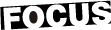
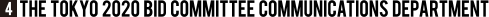
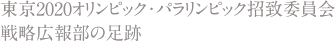
オリンピックに憧れて

招致活動のスタートから約半年、戦略広報部をほぼ一人で切り盛りしていたのは、髙谷正哲だった。肩書きはシニアディレクター代行。組織の中においては、2016年大会の招致活動を経験している数少ない3名のスタッフの一人だった。
髙谷の出身は東京都港区青山。近くには国立競技場、秩父宮競技場があった。子供の頃から彼にとってスポーツとは常に身近にあるものだった。
オリンピックというものに初めて心を強くひかれたのは、バルセロナ五輪のときだ。当時彼は中学2年生で、身体の弱い男の子だった。
女子マラソン、日本のエース有森裕子と金メダルをとったエゴロワのデッドヒート。ブラウン管を凝視しながら、髙谷はあらためてオリンピックのすごさ、そこで活躍するアスリートたちの心と身体の強さを感じ取っていた。
高校では陸上、大学に入るとトライアスロンに打ち込みながら、まだこの新しいスポーツでならと、オリンピックを夢見たこともある。スイムが苦手なこともあって、トライアスロンの世界では結果を出せなかったが、デュアスロン(バイク、ラン、バイクで競われる)では世界選手権にも出場を果たすところまでたどり着いた。
2001年の春、大学を卒業した髙谷は外資系の広告代理店に入社する。5年間、代理店の営業マンとして働いたのち、2006年夏、彼はアメリカのシラキュース大学大学院に入学した。彼が選んだのは広報という分野の学問だった。代理店の営業で学んだノウハウとより深い広報の知識を結びつけることで、何かが生まれる予感があった。なんとかスポーツの世界で、もっと具体的にはオリンピックで、働くことはできないものか?その夢、いや、その目標はこれっぽっちも捨てていなかった。
大学院の卒業資格を得るためには、3ヶ月のインターンを経験しなければならない。その年、大阪では世界陸上が開催されることになっていた。髙谷は事務局にメールを送り、ただでもいいから働かせてほしい、という問い合わせを送った。返事はすぐにきた。あなたのような人材を探している、すぐに履歴書を送ってほしい。
念ずれば通ずる、とはこういうことを言うのだろう。大阪での世界陸上が終わったとき、髙谷は大会の組織委員会で働いていたある人物から、そんなにオリンピックの仕事がしたいなら、2016年大会の招致委員会の仕事を紹介するよ、と誘われる。もちろん断る理由など、どこにもなかった。
2007年11月、髙谷は招致委員会の企画広報部でメディア担当の仕事を始める。仕事の主な内容は、IOC委員たちが常日頃接しているメディアに東京のポジティブなニュースを流し続けることだった。
<次のページへ続く>

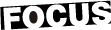
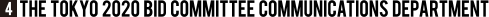
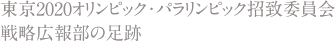
オリンピック・パラリンピックはいかにして決まるのか

写真提供:東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
オリンピック・パラリンピックの招致活動は、現在の規定では、大会開催の9年前にまず申請ファイルを提出することから始める。そのファイルはIOCによって精査され、正式に立候補都市を承認。そしてその1年後、IOCは調査団をそれぞれの国に送り、その結果も詳細なリポートとして公にされるのだ。
立候補した国は様々な招致活動を行えるが、基本的に海外におけるアピ—ルは最終投票の約8ヶ月前までは禁止され、それぞれの委員を自国に招待することもできない。
そして大会開催の7年前、投票権を持つ百数名のIOCの委員たちが投票により開催都市を決定する。委員たちの顔ぶれは各競技団体のトップ、各国のオリンピック委員会の会長、ロイヤルファミリー、アスリート、スポーツ振興に造詣の深い人々が様々な属性で存在する。
IOCとしてはどの国を通過してゆくことがオリンピック・パラリンピックそのものの発展に寄与するかを考えるが、それぞれの委員にはそれぞれのバックボーンがある。競技団体によって開催都市の嗜好は当然変わってくるし、世論によってもIOCの委員たちの方向性が変わってくる。
2009年10月、2016年のオリンピック・パラリンピック開催都市を決める投票はデンマークの首都コペンハーゲンで行われた。勝ったのはリオデジャネイロ、東京は惨敗だった。すべてが初めての経験の中、不眠不休で仕事を続けた髙谷は、投票の結果発表直後、ホテルの椅子で4時間ほどの眠りに落ちた。その後ホテルを出て誰かに会いに行ったが、それがいったい誰だったのか記憶にない。髙谷には選挙の結果はショックだったが、と同時に、翌日には同僚の一人と昼食をとりながら、もう1回やれば勝てるよね、というような話をしていた記憶もある。

長年IOCと深く関わり、この世界のことを熟知している人物の一人、JOC名誉委員(今回の招致活動ではCEOとして全体の指揮に当たった人物でもある)をつとめる水野正人は、この2016年大会の招致活動の敗因をこんなふうに分析する。
「とにかく、リオデジャネイロが強かった。あの当時ブラジル経済は急成長を遂げていたし、IOCの中にも新しい世界でのオリンピック開催という流れもありました。そして何よりも、リオデジャネイロには強烈な熱意というものがありました」
当時リオデジャネイロ招致の陣頭指揮をとっていたカルロス・ヌズマンというブラジルの実力者は、IOCの総会や理事会、あるいはその他にも重要なスポーツイベントがあるたび、宿泊先のホテルのロビーに朝早くから下りてきて、IOCの委員や関係者とにこやかに挨拶を交わし、握手の手を差しのべ、熱意あるロビー活動を繰り広げていた。ブラジルスポーツ界のトップが見せるその姿は、決して通り一遍等の形だけのものではなく、本当にリオデジャネイロはオリンピック・パラリンピックの開催を望んでいるのだということがひしひしと伝わってくるようなものだった。
水野はそんなヌズマンに、あなたの腕は会うたびどんどん長くなっているように見えるよ、と冗談を口にしつつ、同時に、これに比べると日本は劣っているのではないか、と感じていたという。
「結局のところIOCの委員だって人間ですからね。もちろんそれぞれの理事には様々な思惑があり、様々な背景はありますけれど、やはり最後は真心で動くものだと、私は思うんです」
オリンピック・パラリンピックを一つの商品として見れば、東京が提示する2020年オリンピック・パラリンピックは他都市のそれと比べてもまったく遜色のないものだった。いやむしろ、安全面、宿泊面、交通面、それらに関しては間違いなく最高峰のレベルにあった。
であるからこそ、戦略広報部としてはなんとしても、国内支持率を上げ、東京で開催する意義と意味を明確にし、優れたプレゼンテーションを用意し、国内外のメディアにポジティブなニュースを発信し続けなければならなかった。100人余りのIOC委員の一人でも多くになんらかの方法で訴えかけなければならなかった。彼らの意識の中で東京に投票する理由を増やし、東京に投票しない理由を減らし、なぜ2020年は東京でなければならないのか、を強烈にアピールしてゆかなければならなかった。
2012年4月、それまでは髙谷がほぼ一人で切り盛りしてきた戦略広報部は本格的に始動し始める。2016年招致を経験し、いったい何が足りなかったのか、をすでに知っていた髙谷は、人事の構成も含めて上層部にレポートを提出していた。彼に人事の決定権はないが、戦略広報部はスポーツマインドにあふれた人々で構成されるべきだという確固たる確信が髙谷にはあった。同時に彼はこれから先、すでに決定されているIOCのイベントにあわせて、時系列的に、ここはこうする、ここはこうする、という具体的な月ごとの計画表を予算も含めて作成していた。
前回はまったく初めての体験であったがゆえに、コンサルタントのアドバイス通りに動いただけだった。しかし今回は明確な意志を持って、IOCに対してのプレゼンテーションも、誰が、どの機会に、どういうふうに働きかけてゆくべきか、をイメージすることができていたのだ。
<次のページへ続く>

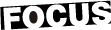
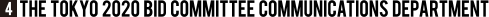
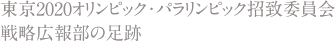
戦略広報部 部長 鈴木德昭

2012年4月、髙谷の上司として戦略広報部のチーフディレクターの座に就いたのは、日本サッカー協会から出向という形で派遣されてきた鈴木德昭だった。
鈴木も髙谷と同様東京で生まれ、東京で育った。父は日立や慶応大学のサッカー部監督もつとめた高名なサッカー選手、自身も兄とともに優れたサッカー選手として青春時代を過ごしている。髙谷とは少し違って、鈴木はオリンピックではなくワールドカップを夢見て育ってきた。
度重なる怪我でサッカー選手の夢はついえたものの、日産自動車入社後はサッカー部の躍進を縁の下で支え、その後は日本サッカー協会に所属して日本代表を率いるハンス・オフトの仕事を補佐。黎明期にあった日本サッカーのプロ化に手を添えてきた。2002年のFIFAワールドカップの招致にも深く関わったキャリアも、戦略広報部 部長の職にふさわしい人物だった。
戦略広報部 部長就任を打診されたとき、鈴木はアジアサッカー連盟の要職に就いていたが、AFCでの任期を少し残したまま、招致委員会の仕事を引き受けることにした。
日本のために、サッカーのために、この二つのキーワードを軸としてこれまでの仕事に携わってきた鈴木にとっては、オリンピック・パラリンピック招致という仕事は己の目的にも叶っている大役に思えた。オリンピック・パラリンピックを呼ぶことで、この国に起こるであろうポジティブな可能性も明確にイメージすることができた。

写真提供:東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
もし東京でオリンピック・パラリンピックが開催されたら?
それぞれの競技団体は明確な目標を持って強化することができる。
予選なしで大会に参加することができる。
間違いなく日本のスポーツ界は一段階上のレベルに到達できる。
強化のための対外試合が増え、それが多様な国際交流にもつながる。
開催国が決定されるIOC委員会まではあと2年。鈴木に与えられた時間はそう多くはない。オリンピック・パラリンピックに関する専門的な動きに関しては、髙谷を全面的に信頼し、彼の決定をバックアップすることを約束した(そしてその約束は最後まで守られた)。
IOCの規則では海外に向けての直接的なPRは翌年の1月7日まではできないことになっている。そこで鈴木はまず国内のいくつかの事案にターゲットを絞ることとした。
一つ目は社内戦略の統一だった。東京2020オリンピック・パラリンピック招致委員会は都庁の41階にあったが、同フロアには東京都の招致推進部も併存していた。お互い目的は同じなのだが、JOC会長と都知事をトップとする二つの組織はうまく情報や価値観を共有できていなかった。招致委員会内の横のつながりをスムーズにすることで、鈴木はさらなるダイナミズムが生まれると考えた。
41階にいる全員が認識すべき価値観、何のためにオリンピック・パラリンピックを東京で開催するのか、東京でオリンピック・パラリンピックを開催することに何の意義があるのか、どういう大会にしたいのか、そのことについてフロアで働く100数名の人間を集め、何度も何度もブレストを重ねることで、それぞれのメンバーが少しずつ共通の価値観をシェアできるようになっていった。ひとつひとつの事案に対して、各部署からかならず誰かが参加してのタスクフォースを構成し、情報の共有度を高めてもいった。
今、ニッポンにはこの夢の力が必要だ。
後に我々が頻繁に目にすることになるコピーも、そういった理念の共有から生まれ出た。水野正人CEOの言葉を借りるなら、戦略広報部の最大の功績は、縦割りの組織だった招致委員会に一本の太い横串をさしたこと、になる。
<次のページへ続く>

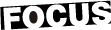
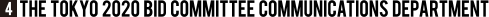
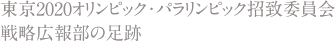
チームワークが成功につながる

写真提供:東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
2013年9月、ブエノスアイレスで開催されたIOC総会で、東京はマドリードとイスタンブールを押さえ、2020年オリンピック・パラリンピックの開催都市に選ばれる。第一次投票では42票、イスタンブール相手の決選投票でも60票を集め、ある意味で盤石な勝負を演じてみせた。
高円宮妃殿下が世界に向けて発した感謝のスピーチから、竹田JOC会長の最後のスピーチに至るまで、戦略広報部が準備したプレゼンテーションは完璧な出来映えだった。
いや、ブエノスアイレスだけではなく、ローザンヌでも、ロンドンでも、今回の招致活動の中で招致委員会が世界に向けてアピールしたそれぞれのプレゼンテーションは、2016年のそれと比べても遥かに効果的で、遥かに説得力を持ち、遥かに熱意に満ちたものだった。

写真提供:東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
懸案だった国内支持率も、ロンドン五輪での日本人選手団の大活躍が後押しとなり、2013年1月の独自調査では73%まで数字を上げることができた。
もちろんそれは戦略広報部で寝る間も惜しんで働き続けた10人だけの業績ではない。招致委員会のトップから、毎週末様々な場所でピンバッジを配り続けた名もないボランティアまで、すべての人々のオリンピック・パラリンピックにかける情熱が、オリンピック・パラリンピック開催に懐疑的だった人々の心を動かした。
あるアメリカ人記者は、震災被害に見舞われた女川町を取材で訪れ、そこに東京五輪招致のポスターが貼ってあることに驚き、被災地の人々までがこの国でオリンピック・パラリンピックが開催される意義を語り、強く応援している姿に心を打たれたという。そしてそういう繊細なニュースを、戦略広報部は世界に対して丁寧に発信し続けていった。

写真提供:東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
人々が目にする東京五輪招致関連のニュース、その裏には必ず戦略広報部の積極的な動きがあったのだ。
チームワークが大事やで。
都庁の41階の片隅に自分の席を設け、招致委員会CEOとして全体を統率し、各部署の動きを見守り続けた水野正人専務理事は、ことあるごとにそう語った。
たとえば野球であれば、ショートゴロのシーンではキャッチャーが必ずファーストの後ろに回るだろう。人間は必ずどこかでミスをする、そのミスを他者がどれだけカバーできるか。部署という枠組みを越えて、互いが互いを補完し合う関係を作ること、その積み重ねが成功につながるのだ、と。
そういう水野CEO自身も、今回の招致には不退転の決意で臨んでいた。彼が会長を務めているミズノは、オフィシャルサプライヤーの一社としてIOCに自社の製品を納入している。利益相反のルール上、会長の立場にある限り招致活動に直接的に関わることはできない。
2011年9月、水野は会長職を辞し、その日からは一人のボランティアとして、会議や打ち合わせに足を運ぶようになった。
<次のページへ続く>

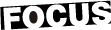
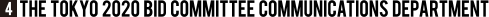
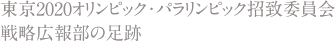
そして2020年、世紀の祭典は東京へとやってくる
2013年9月、ミッションを遂げた戦略広報部は静かに解散し、スポーツがもたらす夢と力を信じて、日夜都庁の41階で働き続けた10人は、それぞれが次の行き先へと去っていった。元いた企業へ戻ったもの、あるいは新しい職場へと移ったもの。
水野正人CEOは再びミズノの会長職に復職し、2020年五輪の大成功をイメージしつつ、日本のスポーツの更なる発展に日々尽力し続けている。
戦略広報部 部長 鈴木德昭は日本サッカー協会に戻り、彼が愛してやまない日本サッカーのさらなる発展と強化に視線を据えている。
そして、戦略広報部の中核を担い、2年間、たぶん誰よりも走り続けた髙谷正哲は、新しい職場を東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 広報局 戦略広報部に見つけた。
長くハードな2年間が過ぎ、しばらくまた海外で違う角度からオリンピック・パラリンピックに携わる仕事を、という願望がなかったわけではない。しかし、最終的に髙谷が選択したのは、招致活動を通じて日本が世界と交わした約束を果たすこと、だった。スポーツの力を世界に向けて発信し、この世界におけるスポーツの価値を高めること、だった。
不眠不休の日々。仕事はきつかったが、そこには他の何にも代え難いような遣り甲斐があった。夜遅くまで続くミーティング、そしてそれが終わると時差のある海外へ向けてのニュースリリース、午前5時にようやく一日の仕事が終わるのはざらだった。肉体は悲鳴を上げていた。しかし、都庁の41階から眺める明け方の東京の街は、髙谷の目にはこの上なく美しく素敵な街に思えた。冷えきった冬の空気の中、髙谷正哲は自分が生まれ育ったこの街に、そしてこの国に、オリンピック・パラリンピックが来ることの凄さをいつも感じていた。
2020年7月、そのオリンピック・パラリンピックは、本当に東京にやってくる。

<了>
写真・文
近藤篤
ATSUSHI KONDO
1963年1月31日愛媛県今治市生まれ。上智大学外国語学部スペイン語科卒業。大学卒業後南米に渡りサッカーを中心としたスポーツ写真を撮り始める。現在、Numberなど主にスポーツ誌で活躍。写真だけでなく、独特の視点と軽妙な文体によるエッセイ、コラムにも定評がある。スポーツだけでなく芸術・文化全般に造詣が深い。著書に、フォトブック『ボールピープル』(文藝春秋)、フォトブック『木曜日のボール』、写真集『ボールの周辺』、新書『サッカーという名の神様』(いずれもNHK出版)がある。