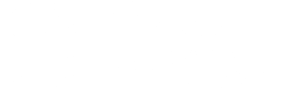スポーツチャレンジ賞

近藤篤 = 写真・文
Text&Photograph by Atsushi Kondo
もしもある日、自分の目が見えなくなったら、それでも僕はスポーツをやろうとするだろうか?もしもある日、車椅子の生活が始まったら、それでも自分はスポーツをやりたいと思い続けるだろうか?そんなことをたまに考える。
第8回ヤマハ発動機スポーツ振興財団スポーツチャレンジ賞功労賞を受賞した藤原進一郎さんを、大阪市長居障がい者スポーツセンターに訪ねたのは、6月上旬のよく晴れた午前だった。
地下鉄御堂筋線を長居駅で降り、一番出口から北へおよそ200mほど歩いたところに,その施設はあった。築40年、クリーム色を基調とした二階建ての建物はやや古びてはいるものの、エントランスの大きな天窓から差し込む光は場内を優しく照らし、スポーツウェアに身を包んだ利用者がひっきりなしに出入りしている。1階中央には大きなホール、その周りにはプール、体育室、トレーニング室が配置され、ホールから伸びるスロープはなだらかな弧を描いて2階へと続いてゆく。

藤原さんがこの施設の初代指導課長として就任したのは、1974年の春のことだ。彼はそれまで大阪市で中学校の体育教師を務めており、最後に教鞭をとった平野中学では体育の模範授業で全国表彰を受けるほどだった。しかし41歳のある日、藤原先生はこれまでと少し違う道を歩むことを一人で決断する。
「今でも家内の機嫌が悪いと言われるんですよ、ようまああれだけ重要なことを誰にも相談もせんと勝手に決めたわね。あのまま教師を続けてたら、今頃はどんだけ楽できてますかねえ、って」
確かに、そんな大切なことを自分一人で決めたのは良くない。でも、藤原先生の奥様には申し訳ないが、その決断のおかげでこの国の障がい者スポーツ界は、唯一無二、かけがえのない人材を手に入れることができた。
指導課長に就任した藤原先生には、スポーツはすべての人々に必要なのだ、という信念があった。
「健常者にとってもそうですが、障がい者にとっては尚更、スポーツというのは大事なものなんです」
全国で初めての『障がい者のための』スポーツ施設。それだけでもこの長居障がい者スポーツセンターは時代の一歩先を行く施設だったが、藤原先生はさらに革新的な概念を持ち込む。 センターを利用しに来てくれる人たちはみんな『お客さん』。たとえ障がい者であろうと、スポーツを楽しみに来る彼らは、患者でもなければ訓練生でもない。巷に数多あるスポーツジムと同じように、ここに足を運ぶ人々は誰もが一人の顧客として扱われるべき、それが藤原先生の考え方だった。

「でもね、この『お客さん』という考え方を当時は「危険思想」とまで表現する関係者もいたんですよ」
今から40年前、日本における障がい者スポーツとは、あくまでも治療やリハビリのために存在するものであり、真剣に楽しみ、競い合うものではなかった。藤原先生はそこに、健常者であろうが、障がい者であろうが、スポーツはスポーツ以外の何物でもない、という極めて当たり前の理屈を持ち込んだわけだ。
先生は強い口調で言う。だから、障がい者のスポーツ、なんてものはないわけです。ただ、ルールが違うだけですよ。ルールというのは要するに競技者にどう負荷をかけるか、ということなんです。
施設の団体使用は極力制限し、あくまでも個人がいつでも使いたい時に使え、やりたい競技をやれる。卓球教室があり、水泳教室がある。例えば一人で卓球場に行っても、そこには若いインストラクターがいて、いつでも卓球の相手をしてくれる。そんな素敵な場所が大阪に、しかも主要な交通機関を使えばすぐに行ける場所にできたわけだから、大きなムーブメントが起こらないわけがない。
スポーツの究極の目的は仲間づくり。藤原先生の目論見は見事に当たり、この長居のスポーツ施設からは卓球クラブ、水泳クラブ、様々な競技団体が次々と生まれては育ってゆき、やがて彼らの手による全国規模の大会も催されるようになっていった。
すごいですねえ。施設の別棟にある会議室で、静かに語る先生の言葉に耳を傾けながら、僕は何度も深く頷き、感心する。しかし当の本人はその度、いやいや別に大したことはやってません、と軽く受け流すだけだ。まるで、湖面に石を投げたら誰が投げたって水紋は広がるやろ、という風に。
「それが誰でもよかったわけではないでしょうが、まあたまたま私だったということでしょう。頼まれたら引き受ける、それが教師というものじゃないですか」

教師の道を半ばで逸れ、新しい世界へと踏み込んでいった藤原進一郎は、結局最後まで頼りになる先生だったということだ。
先生が大事に育て上げた長居障がい者スポーツセンターの利用者は、今年2016年9月11日、1000万人を達成した。このスポーツ施設を通り過ぎていった1000万人の流した汗と、悔し涙と、喜びの声を思うとき、改めて藤原先生の存在の大きさを知らされる。
インタビューは二時間半ほど続いただろうか。最後に写真の撮影をして、僕は再びメインエントランスを抜けて外へと出る。上空には夏の到来を告げる美しい青空が広がり、どこかで誰かが、ほなまた明後日、頑張ろな!と声をかけるのが聞こえる。ここでは、スポーツはあくまでも日常にあるもの、なんら特別なものではない。
僕はもう一度考えてみる。
もしもある日、目が見えなくなったら、それでも僕はスポーツをやろうとするだろうか。もしもある日、車椅子の生活が始まったら、それでも僕はこの世界を駆け続けたいと願うだろうか。
大阪市長居障がい者スポーツセンター。もしもその時、ここにこんな施設があることを知っているなら、それでもやっぱりスポーツを続けてみよう、と思えるかも知れない。
「スポーツチャレンジ賞」トップにもどる