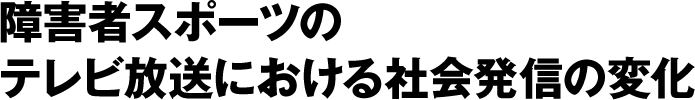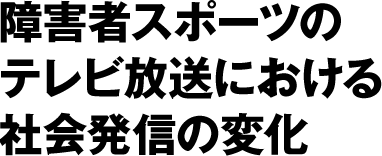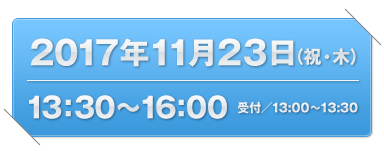レポート
2017年11月23日
シンポジウム2017「障害者スポーツのテレビ放送における社会発信の変化」を開催しました

シンポジスト報告
パネルディスカッション
2020年に向けた抱負
パネリスト・スペシャルインタビュー編
若山 英史さん(ウィルチェアーラグビー選手 リオ2016パラリンピック日本代表)
佐藤 圭太さん(陸上選手 リオ2016パラリンピック日本代表)
太田 慎也さん(WOWOWチーフプロデューサー)
刈屋 富士雄さん(NHK解説主幹/スポーツ担当)
ヤマハ発動機スポーツ振興財団は、11月23日(木・祝)、東京・弘済会館にてシンポジウム2017「障害者スポーツのテレビ放送における社会発信の変化」を開催しました。本シンポジウムは、当財団が平成24年度から取り組んでいる「障害者スポーツを取り巻く環境課題の調査研究」の一環として実施したものです。
障害者スポーツをテーマとしたシンポジウムは、平成26年度の「日本のパラリンピック選手強化の現状と課題」(神戸と東京の2会場で開催)、平成27年度の「パラリンピック選手発掘・育成・強化システムの現状と今後の方向性について」、そして平成28年度の「障害者スポーツ選手発掘・育成・強化システムのモデル構築に向けて」に続いて5回目の開催。メディア露出の拡大により障害者スポーツへの社会的関心の高まりを感じる中、特に影響度の高いテレビ放送環境の変化を踏まえ、障害者スポーツ放送の在り方や今後の期待などについて来場者の皆さんとともに考えました。
当日は当財団障害者スポーツ・プロジェクトを代表して小淵和也氏(公益財団法人笹川スポーツ財団 主任研究員)が平成28年度の調査研究結果を報告。また、プロジェクトリーダーの藤田紀昭氏(日本福祉大学スポーツ科学部 教授)をコーディネーターに、パネルディスカッション「障害者スポーツとテレビ放送の関係性」を実施しました。
パネルディスカッションでは、放送メディアの立場からWOWOW「パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM」チーフプロデューサーの太田慎也氏とNHK解説主幹(スポーツ担当)の刈屋富士雄氏が、アスリートの立場から陸上の佐藤圭太選手とウィルチェアーラグビーの若山英史選手がパネリストとして参加して活発な意見交換を展開。プロジェクト・アドバイザーとして参加した中森邦男氏(公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 強化部長、日本パラリンピック委員会 事務局長)は、「長年障害者スポーツに携わってきて、社会の関心という点でさまざまな難しさを感じ続けてきた。しかし、今日の素晴らしいディスカッションを聞いて目からウロコが落ちた気持ち。発想を転換することで道が拓けるという可能性を感じることができた。お集りの皆さんに感謝したい」と述べました。
平成28年度調査結果および課題報告
小淵 和也さん(公益財団法人笹川スポーツ財団 主任研究員)
 パラリンピックにおける障害者スポーツの地上波テレビメディアでの露出状況を把握するため、「障害者スポーツのテレビ放送における社会発信の変化」について調査研究してきました。その一部を紹介します。
パラリンピックにおける障害者スポーツの地上波テレビメディアでの露出状況を把握するため、「障害者スポーツのテレビ放送における社会発信の変化」について調査研究してきました。その一部を紹介します。
過去3大会の比較では、北京、ロンドン、リオと大会を重ねるにつれ放送時間が増えているのがわかりますが、たとえばNHK総合がロンドンからリオでは3倍以上に拡大しているのに対し、NHK教育では半減しています。これは、NHKがロンドン大会ではパラリンピックを障害福祉ととらえていたのに対し、リオ大会ではスポーツとしてとらえなおしたものによるものと推測されます。また、番組カテゴリー別に見ると「情報/ワイドショー」「ニュース/報道」が大きく伸びているのに対し、「スポーツ」番組ではロンドンとリオで変わりはありませんでした。パラリンピックやパラリンピアンが、さまざまな角度で伝えられ始めていることがうかがえます。
このようにテレビによる情報露出が大幅に増えている一方で、パラリンピアンの社会的認知は高まっていません。このプロジェクトではパラリンピアンの認知度調査も行ったのですが、車いすテニスの国枝慎吾選手が最もよく知られていて34.0%。リオ大会でメダルを獲得した陸上の辻沙絵選手は5番目で、わずか6.1%です。国枝選手でさえ3分の2の人々が知らないわけです。本日は情報を発信する側の皆さんにパネルディスカッションをしていただきますが、その情報を受ける側がもっと関心を深められるような、そんな視点でも議論をお願いできたら幸いです。
佐藤 圭太さん(陸上選手 リオ2016パラリンピック日本代表/世界パラ陸上ロンドン2017日本代表)
 私は小・中学校で年間20〜30回ほど講演をさせてもらっています。その際、生徒の皆さんに「義足を使っている人を実際に見たことがあるか?」と質問するのですが、手を挙げるのはだいたい1割程度。でも「テレビで見たという人は?」と聞くと、「はーい」とほぼ全員が手を挙げます。「パラリンピックの放送を見た」という子もいれば、「24時間テレビで登山する人を見た」という子もいます。いずれにしても子どもたちはテレビを通じて、義足や義足を使っている人を認知しています。
私は小・中学校で年間20〜30回ほど講演をさせてもらっています。その際、生徒の皆さんに「義足を使っている人を実際に見たことがあるか?」と質問するのですが、手を挙げるのはだいたい1割程度。でも「テレビで見たという人は?」と聞くと、「はーい」とほぼ全員が手を挙げます。「パラリンピックの放送を見た」という子もいれば、「24時間テレビで登山する人を見た」という子もいます。いずれにしても子どもたちはテレビを通じて、義足や義足を使っている人を認知しています。
一方で、私の義足を見た子どもたちの反応は、「うわー」と声を出して、驚いたような、怖がってもいるような印象です。大人たちは少し違うのですが、「助けなきゃ」とか「かわいそう」とか、そんなふうに感じるようです。私が願っているのは、「見たことがある」「知っている」からもう一歩進んだところにある、障害に「なじむ」という社会。そういうふうに社会の人々の心がマインドセットされるために、私たち選手は競技力を向上することでより強く発信しなければと考えています。
私の実感としては、2020東京大会が決まってから、テレビで「パラリンピック」という言葉をよく聞くようになりました。特にリオ大会以降、メディアの皆さんが、パラリンピックやパラ選手を盛り上げていこう!と意識してくださっているのを実感しています。私自身もパラ選手を扱う特番などに何度か出させていただきました。2020でメダルを獲っておしまいではなく、そうした「なじむ」社会の契機にしていけたらと考えています。
若山 英史さん(ウィルチェアーラグビー選手 リオ2016パラリンピック日本代表)
 おかげさまでウィルチェアーラグビーという競技について、テレビや雑誌で取り上げてもらうことが多くなりました。競技自体の認知は高まっていると感じています。一方で報道する皆さん、会場やテレビで競技を観る皆さんにより理解を深めていただきたいという思いを持っています。
おかげさまでウィルチェアーラグビーという競技について、テレビや雑誌で取り上げてもらうことが多くなりました。競技自体の認知は高まっていると感じています。一方で報道する皆さん、会場やテレビで競技を観る皆さんにより理解を深めていただきたいという思いを持っています。
ウィルチェアーラグビーは、軽度の障害から重度の障害までポイントでクラス分けされたチームスポーツです。私は重いほうから2番目のポイントで、チームの中ではローポインターという立場です。一方、軽度のハイポインターはボールを長く持ち、ゲームの中でも非常に目立つ存在です。ですからマスコミの皆さんの視線もそちらに向きがちなのですが、あくまでチームで戦う球技ですから、誰か一人の力で勝つことはできません。ローポインターは、ハイポインターにゴールまでボールを運ばせるため、道をつくり、盾にもなります。そうした、いぶし銀の働きなど、チームがどのように成り立っているのか、そのあたりを視聴者の皆さんに伝えていただきたいと願っています。
非常に激しいスポーツですから、観た人は心の中にある何かを覆させられると思います。そうしたインパクトだけではなく、我々ローポインターが相手のハイポインターを技術や経験で止める見どころをしっかり伝えていただき、また見ていただけたら嬉しいです。
太田 慎也さん(WOWOWチーフプロデューサー)
 2年前から世界中のパラスポーツのトップアスリートを追いかけて、「WHO I AM」というドキュメンタリー番組を作っています。5年間にわたって、毎年8人のパラアスリートに密着するIPC(国際パラリンピック委員会)との共同プロジェクトです。WOWOWのような有料放送がなぜそのような取り組みをするのか、皆さんも不思議に思うかもしれません。
2年前から世界中のパラスポーツのトップアスリートを追いかけて、「WHO I AM」というドキュメンタリー番組を作っています。5年間にわたって、毎年8人のパラアスリートに密着するIPC(国際パラリンピック委員会)との共同プロジェクトです。WOWOWのような有料放送がなぜそのような取り組みをするのか、皆さんも不思議に思うかもしれません。
21世紀に入り、世界はグローバル化に向かい、コミュニケーションツールも発達し、そんな中、日本では東日本大震災以降「つながり」や「結束」という言葉が溢れています。しかし、人とつながることが優先されるあまり「個」が埋もれ、人が自分と向き合う機会を失くしているのではないかと感じています。「自分について語ることができるか」「これが自分だ!という主張はあるか」。世界のパラアスリートは、競技だけじゃなく、人生についても自信に満ち溢れています。メディアとして世界最高峰の選手たちと向き合うとともに、視聴者には自分と向き合ってほしい。そういう思いを込めてタイトルを「WHO I AM」としました。私たちはこの志を忘れないよう、「フィロソフィー」として文章にまとめて、ことあるごとにそれを読み返しています。
私たちは有料放送の小さな局ですが、パラアスリートたちが情熱を持ち、人生をエンジョイしている姿を伝えながら、2020年、そしてその先に向けて貢献したいと考えています。海外のパラアスリートは、皆口をそろえて「東京はアメージングな大会になる」と期待しています。ハードだけでなく、ソフトもますます充実して、選手たちがエンジョイできる大会となるよう願っています。
刈屋 富士雄さん(NHK解説主幹/アナウンサー/リオ五輪ニュース情報番組 解説委員)
 私は33年間、スポーツの現場に立ってきましたが、パラリンピックを中継した経験が一度もありません。NHKでは長いこと、パラリンピックは生活情報系、福祉系の分野に位置づけられてきました。北京パラリンピックがEテレで中継されたのもそのためです。
私は33年間、スポーツの現場に立ってきましたが、パラリンピックを中継した経験が一度もありません。NHKでは長いこと、パラリンピックは生活情報系、福祉系の分野に位置づけられてきました。北京パラリンピックがEテレで中継されたのもそのためです。
北京大会の後「本当にそういう姿勢で良いのか?」という議論が沸き起こり、ロンドン大会では初めてアナウンサーが現地から実況しました。続いて2015年にはNHKの中にパラリンピック研究会というものができ、頻繁に研修・研究を行うようになりました。その最初のテーマは「何がわからないのか、まずそれを知ろう」というものでした。わからないことがわからない、そんなレベルだったのです。それでは、いまはわかっているのかと聞かれると、その逆です。「何を伝えるべきか?」「どう伝えるべきか?」、ますます悩みは深まるばかりです。
それでも体制は大きくなってきて、リオ大会では13人のアナウンサーが現地から伝えました。東京のスタジオから伝えたアナウンサーを含めると22人の体制です。さらに2020東京に向けて、その倍以上のアナウンサーの育成を目指しています。また女性の障害者キャスター2名を決定し、こうしたメンバーがNHKのパラ中継の顔になっていく予定です。